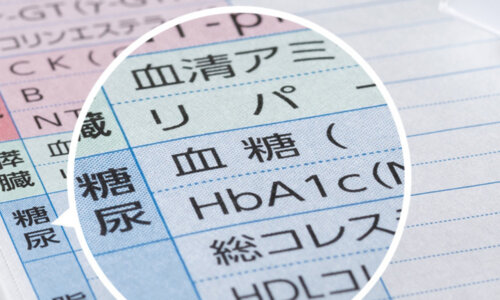弊社の商品開発チームの医師監修
Q. 糖尿病で食事療法を行っていますが、麺類を食べるときには「うどん」と「そば」は、どちらを選ぶべきですか?
A.うどんよりそばの方が糖質量は多いことがわかっています。しかし、血糖値の上がりやすさを示すGI値は、うどんが85、そばは54となっているため、そばの方がおすすめです。
目次
そばが糖尿病に良いと言われる理由
糖尿病と診断されて食事療法を行っている患者さんの中には、「炭水化物が食べたい。そばなら良いの?」と思う人も多いのではないでしょうか。
麺類のなかでも「そば」は糖質量が比較的少ないといわれており、糖尿病患者さんの炭水化物の選択肢としてはおすすめです。
前述した通り、うどんのGI値が85、白米が88に対して、そばのGI値は54ほど。GI値が低いと、食品に含まれる糖質を分解する際に使うインスリンの量が少なくて済むため、食事をした後の血糖上昇スピードが比較的ゆるやかになります。
1日3食、必ず白米を食べている場合には、そのうちの1食をそばにすることで、血糖値の上昇を防ぐ効果が期待できるかもしれません。
ほかにも、そばが糖尿病に良いとされる理由は、含まれる栄養素にあります。
そばにたっぷりと含まれているのが、ビタミンB1やビタミンB2。白米や小麦と比較すると、およそ2~3倍にもなるため、普段からビタミンB群が不足しがちな糖尿病患者さんにはおすすめです。
また、そばにはポリフェノールの一種である「ルチン」という成分が含まれていて、膵臓機能を活性化して血圧や血糖値の上昇を抑える働きが期待できます。
毛細血管を強くしなやかにする作用もあるため、糖尿病の合併症に多いとされている動脈硬化や心筋梗塞、脳梗塞などの予防に効果的です。
そばを食べても血糖値が上がりにくいって本当?
前述した通り、そばは炭水化物の中でも、比較的、糖質量が少ない食品とされています。
本当に血糖値が上がりにくいのか? ほかの炭水化物と比較してみましょう。
蕎麦やうどんの血糖値影響を比較
| 主食 | GI値 | 糖質量 100gあたり |
|
| 1 | そば | 54 | 24g |
| 2 | 玄米ごはん | 55 | 34g |
| 3 | パスタ | 65 | 28g |
| 4 | ラーメン | 75 | 28g |
| 5 | うどん | 85 | 21g |
| 6 | 白米 | 88 | 37g |
| 7 | 食パン | 95 | 69g |
血糖値の上がりやすさを表すGI値の低さに関しては、炭水化物の中ではそばがNO.1という結果が出ています。低糖質ダイエットや糖尿病の炭水化物の選択肢として、人気が高いことにも頷けますね。
実際、100gあたりの糖質量を比較すると、うどんは21g、そばは24gほどで、実はそばの方が糖質量は多いという結果が出ています。
しかし、血糖値の上がりやすさは、単純に糖質量の多さで決まるものではありません。うどんより糖質量が多いにも関わらず、そばのGI値が低いのは、そばに含まれる食物繊維が大きく関わっています。食物繊維は、腸内で糖が吸収されるのを抑制して、血糖値を急激に上昇させないように働いてくれるのです。
ですので、精製された小麦粉を主原料としているうどんより、蕎麦粉を使用して作られた「そば」の方が糖尿病患者さんの血糖コントロールには優しいといえます。
糖尿病の人には「十割そば」がおすすめ
そばを選ぶ際は、小麦粉の量にも着目しましょう。
スーパーでよく見かける「二八そば」は、実は蕎麦粉が2割しか使われておらず、8割は小麦粉で作られています。小麦粉が多く入っているものほど、それだけGI値もうどんに近づいていくため、注意が必要です。
一方、糖尿病の人が選ぶなら、十割そばがおすすめです。十割そばには小麦粉が一切使われておらず、蕎麦粉の食物繊維やミネラルなどもたっぷり摂ることができます。
ただし、十割そばをはじめ、「そばは糖尿病に良いから、お腹いっぱい食べよう!」といった考えを持つのは危険です。そばの糖質量が少ないのは、あくまでも炭水化物のなかでの話しです。十割そばと言えど、野菜やきのこ類、海藻類に比べるとGI値も糖質も高いことに変わりはありません。
食品全体から見ると、麺類をはじめとした「炭水化物」は、血糖値を上げやすい食べ物であることを忘れてはいけません。
とくに糖尿病を発症している患者さんは、食べ方や食べる量に注意が必要です。
糖尿病でもそばや炭水化物が食べたい!血糖値を急上昇させないコツ
炭水化物の中では血糖値を上げにくいとされる「そば」ですが、注意したいのが、つるつると食べやすいために「早食い」や「食べ過ぎ」が起こりやすいことです。
GI値の高さ以上に、「早食い」や「食べ過ぎ」は血糖値を上げる大きな要因となります。
では、そばや炭水化物を摂る際は、どうしたら良いのでしょう?ここでは、血糖値の急上昇を防ぐ食べ方のコツをご紹介します。
1:食後血糖値をコントロールする
糖尿病の悪化を防ぐために最も避けるべきことが、急激な血糖値の上昇です。
食後に血糖値が急上昇し、その後、急降下する状態のことを「血糖値スパイク」といいますが、糖尿病の人が血糖値スパイクを起こすと、低血糖状態になり、時には気絶してしまうこともあります。ほかにも、血糖値スパイクにはさまざまな合併症のリスクがあり、糖尿病を進行させる原因にもなりかねません。
血糖値スパイクに限らず、食後に血糖値が急上昇すると、インスリンの分泌量が一気に上がり、インスリンを分泌するすい臓も疲弊してしまいます。それによって、さらにインスリンが出にくくなって血糖値が上がり…と、悪循環を起こしてしまうのです。
「早食い」や「食べ過ぎ」が良くないのは、これが理由です。
だからこそ、つるつると食べられるそばや麺類には注意しましょう。
では、食後血糖値の急上昇を防ぐには、どうすれば良いのか?
その方法はカンタンです。血糖値をコントロールすれば良いのです。
血糖値が上がるのは食事の時。ですので、食事開始後、30分、60分、90分、120分の血糖値をしっかりコントロールしましょう。
ここさえコントロールできれば、血糖値の急上昇は大半を防げます。
まずは食後の血糖値を測定してみて、食後30分〜120分の間の血糖値を140に抑えることができればOKです。それにより、血管内に糖が溢れるのを防ぎ、脂肪の吸収も防ぐことができます。
血糖値の測定が有効なのは、糖尿病の人だけではありません。プロのボクサーも試合前に減量をする時は、血糖値を測りながら、少量の食事を1日5回などに分けてゆっくり食べています。
血糖値が気になる場合や痩せたい場合は、ぜひこの方法を取り入れてみて下さい。
2:食後の〇〇で糖の吸収を防止!
早食いやドカ食いが良くないとはいっても、お腹が空いている時はついつい食べてしまいますよね。
そんな時は、糖の吸収を抑える『フェーズ2プラス』がおすすめです。
食事の30分前にたっぷりの水と一緒に摂ることで、
特許成分「フェーズ2」と「ギムネマ」の2つの成分が、食べた糖を吸収させず、便としてそのまま排出します。
その効果は、最大66%の糖をブロックできることが臨床試験で実証済み。
さらに、もうひとつの特許成分「クロムメイト」がすでに蓄積した脂肪も分解してくれるので、ダイエットにも効果が期待できます。
フェーズ2プラスを摂る際は、食事の30分前に水をたっぷりと飲むのがポイント。これで食欲も抑えられるでしょう。
また、食後血糖値が140を越えている場合は、軽い運動を取り入れるのがおすすめです。
血糖値が140を越えた時点で、いったん食べるのは止めて、スクワットを50回するなどして糖を燃焼させます。食後に軽いウォーキングをするのも有効です。
この他に、血糖値の急上昇を防ぐのに避けるべきものとしては、
・コーラなどの清涼飲料水
・甘いコーヒー
・野菜ジュース
などの糖質が多いドリンクが挙げられます。とくに健康に良いと思われている野菜ジュースは、糖質量が半端ないので避けましょう。
3:インスリン分泌を促す栄養素を摂る
すでに糖尿病を発症している人で「徹底的に糖質をブロックしたい」、「血糖値をコントロールしたい」場合は、インスリンの分泌を促す栄養素を摂るのが有効です。
食事と一緒に取り入れやすいものには、ハーブティーがあります。

ドクターズチョイスの『グルコティー』には、糖尿病専門医が推奨する8種のハーブを配合。食事と一緒に飲むことで、徹底的に糖の吸収をブロックし、血糖値の急上昇を防ぎます。カフェインフリーなので、夕食時にも思いっ切り飲むことができますよ。
すでに糖尿病を発症していて、インスリンの働きが悪い方は、「亜鉛」を積極的に摂りましょう。糖尿病の人は健常者に比べ、血中の亜鉛が少ないというデータがあり、糖尿病患者の3人に2人は亜鉛不足といわれています。
さらに、インスリンの働きを良くするには、「クロム」と「マグネシウム」も欠かせない成分です。糖尿病の人は日頃、健常者の3倍の量の「亜鉛」と「クロム」が尿から排出されています。
これら3つの成分をすべて配合しているのが、
ドクターズチョイスの『グルコサポート』です。
糖尿病の人に不足しがちな3種のミネラルのほか、血糖値の上昇を抑え、インスリンの働きをアップさせる14種の有効成分を一度に摂ることができます。
ハーブ由来の成分なので、薬とは違い、副作用なく毎日お飲みいただけます。
ぜひ、食後血糖値の変化や、ヘモグロビンA1Cの数値の変化をご実感ください。
4:糖質ゼロの食品を取り入れる
血糖値を急上昇させないためには、糖質ゼロの食品を取り入れるのも有効です。糖質ゼロの食品というと「美味しくない」イメージがあるかもしれませんが、ドクターズチョイスでは、この度、糖尿病の人にとって心強い味方を導入しました。
それが、奇跡の甘味料と呼ばれる『アルロース』。

アルロースは、イチジクやレーズンなどの果物に微量に含まれている希少糖です。
実質糖質ゼロ・カロリーもゼロ。それでいて驚くほど砂糖に近い美味しさということから、近年、健康志向の高まりとともに注目を集めています。
砂糖の代わりにアルロースを使うことで、甘みの強い煮物やすき焼き、さらには食後の甘いコーヒーも糖質を気にせず、楽しめるようになります。低糖質の味気ない食事が一気に華やかになり、毎日の食事の満足度がぐんと高まるでしょう。
アルロース専門店では、調理に使う天然甘味料・アルロースのほか、アルロースを使った至福のスイーツも販売しています。
糖尿病のそばの食べ方 Q&A
糖尿病患者がそばを食べるときの適正量は?
いくらGI値が低いとは言え、そばも血糖値を上げやすい麺類の一種なので食べ過ぎは禁物です。
日本糖尿病学会が発行している「糖尿病食事療法のための食品交換表」によると、そばは乾燥20g、ゆで麺60gが1単位となっています。白米の場合は1単位50gですが、一食でお茶碗1杯分にあたる2~3単位(100~150g)を摂取している人が多いかもしれません。
ですので、普段から150gのご飯を食べている方は、そばに置き換えると乾燥麺60gまたは、ゆで麺180gが適正量となります。
ただし、主食から摂取すべきカロリーは、身長、体重、年齢、活動量によっても異なります。糖尿病の人が主食の単位数を決めるときには、普段の食生活を基準にするのではなく、身長と標準体重、活動量から算出した「適正エネルギー」をもとに、しっかりと計算してコントロールするようにしましょう。
糖尿病によいそばのレシピやメニューは?
糖尿病の人がそばを食べる際は、具がたくさん乗っているそばよりシンプルな「かけそば」や「ざるそば」を選んだ方が、カロリーが低くて良い気がするかもしれません。
しかし、これは大きな勘違いです。
かけそばやざるそばはカロリーこそ低いですが、炭水化物を単品で摂取することは、食後の血糖値の急上昇を招きます。簡単に言えば、おかずをまったく食べず、白米だけを摂取しているのと同じような状況です。
糖の吸収を抑制するためには、そばを食べる際にも食物繊維やたんぱく質と一緒に摂ることが大切です。
特に、わかめなどの海藻類や、山菜、ねぎ、ほうれん草などの野菜類のトッピングをたっぷり乗せるのがおすすめです。鶏肉や卵などのたんぱく質が豊富な食品をプラスするのもよいでしょう。
また、糖尿病には揚げ物がよくないといったイメージがありますが、そばを単品で食べるくらいなら「野菜のかき揚げ」や「海老の天ぷら」などが乗ったメニューを選んだ方が、血糖コントロールにはよいとされています。
外食する場合は、丼ものとそばのセットなど「炭水化物の重ね食い」は避けるようにしてください。ランチメニューでは、お得な料金で提供されていることが多く、ついつい選んでしまいたくなるものですが、糖尿病患者さんの血糖コントロールを大きく乱す恐れがあるので注意しましょう。
食後の蕎麦湯は糖尿病でも飲んでいいの?
糖尿病を患っている人は、高血圧や高血糖に注意しなければならないため、蕎麦湯で薄めてまで「残りのつゆ」を飲み干すことはおすすめできません。
そもそも蕎麦湯は、残ったつゆを最後まで美味しく飲むために活用されています。そばつゆには、醤油をはじめ、砂糖やみりん、鰹節などの出汁がたっぷり。美味しさと引き換えに、多くの塩分と糖分が含まれているのです。
もちろん、蕎麦湯にはさまざまな栄養素も溶け込んでいますが、そば自体にも同じ栄養素が含まれているので、わざわざ食後に蕎麦湯を飲む必要はないでしょう。
まとめ
糖尿病の治療は、食事療法と運動療法が大きな柱となります。カロリーや糖質、脂質の摂り過ぎに注意しながら適度な運動を行うことで、良好な血糖コントロールを継続することが可能です。
しかし、糖尿病患者さんでも「麺類が食べたい」と思うことも少なくないでしょう。そんなときは、炭水化物の中でもGI値の低いそばを選ぶのはおすすめです。
ただし、そばはGI値が低い反面、つるつると食べやすく、早食いや食べ過ぎが起こりやすい食品です。それによってかえって血糖値が急上昇するリスクもあるので、糖尿病の人は血糖値コントロールを行いながら、食べ方や食べる量には注意しましょう。
ドクターズチョイスでは、血糖コントロールに欠かせない「血糖値測定器」をはじめ、「糖の吸収を抑えるサプリメント」、「実質糖質ゼロ・カロリーゼロの天然甘味料」など、日々の血糖値コントロールに役立つ様々な商品を扱っています。
これらの商品を上手に取り入れながら、糖尿病の治療をストレスなく継続していくとよいでしょう。
アメリカ、カナダ、ブラジルの3カ国で認定された国際免許を取得している自然療法専門医。
スコッツ先生のプロフィール