目次
糖尿病と体重に関する基礎知識
弊社の商品開発チームの医師監修
Q. 糖尿病って痩せていても患うの?
A. 糖尿病は痩せている人も患うことがあります。
急な体重減少は糖尿病の症状のひとつ
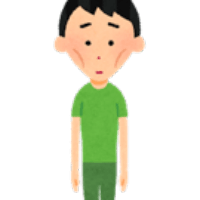 「運動もしていないのに少しずつ体重が減っている」
「運動もしていないのに少しずつ体重が減っている」
「急激に体重が減った」
こんなことはありませんか。
もしかしたら、糖尿病が原因かもしれません。
糖尿病は食生活の乱れや運動不足により、血液中の糖が増えることで引き起こされる病気です。
また糖尿病は太っている人だけが患う病気ではありません。
痩せている人もまた糖尿病を患うことがあるのです。
こちらの記事では、
- 糖尿病で体重が減少する仕組み
- 糖尿病の種類とその症状
- 痩せている人が糖尿病を患う可能性
- 糖尿病が引き金となり患う合併症の恐ろしさ
- 糖尿病患者が増加している背景
- 糖尿病対策
についてわかりやすく解説しています。
糖尿病による体重の減少についての概要をまとめていますので是非ご一読ください。
糖尿病とは?どうして糖尿病を患うと体重が減少するのか
糖尿病が原因で体重が減少する仕組みを解説します。
私たちはお米やパンといった炭水化物、イモ類からブドウ糖を補給しています。
食事をすることで取り込まれたブドウ糖は血液中に溶け込み脳や筋肉、内臓に行き渡り、私たちが活動するためのエネルギー源となります。
この血液中のブドウ糖のことを血糖といいます。
健康な人の場合、すい臓で生成されるインスリンというホルモンの働きにより血糖が一定の幅で保たれています。
食事によって血糖値が上がるとすい臓がインスリンを分泌します。
血糖が各臓器に行き渡ると体を動かすためのエネルギーになったり、タンパク質を合成したり、細胞の増殖を促したりします。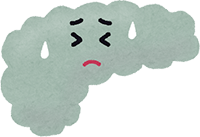
このように食後に増加した血糖はさまざまなエネルギーに変換されることで一定量に保たれているのです。
しかし何かしらの原因でインスリンの量が不足したり、働きが悪くなると血糖が高い状態が続きます。
血糖が一定の値を超えて高い状態が続くことを高血糖といい、この状態が糖尿病というわけです。
高血糖の状態が続くと喉の渇きを感じたり、お手洗いに行く回数が増えます。
高血糖になることで、浸透圧により体の中から外へと水分が排出されるようになります。
その結果、脱水症状を引き起こしてしまいます。
血糖値を下げない限り、仮に水を飲んだとしても尿として排出されていきます。
インスリンの働きが弱まったことで補給したブドウ糖が各臓器に行き渡らなくなります。
臓器を働かせるためのエネルギー源が不足するため、体にある脂肪や筋肉といったタンパク質がエネルギーとして分解された結果、体重が減少していくのです。
糖尿病の種類とその症状とは
尿病には1型糖尿病と2型糖尿病の2種類があります。
それぞれの特徴について解説していきます。
1型糖尿病はインスリンの欠乏により引き起こされる糖尿病です。
糖尿病患者の1割が1型糖尿病を患い、年齢に関係なく発症します。
主な症状は
- 喉が渇く
- 尿の回数が増える
- 急激に体重が減少する
- ひどい疲れを感じる
です。
1型糖尿病の原因はいまだに解明されていませんが関係のある要因として
- もともと1型糖尿病を患いやすい体質を持っている
- インスリンを分泌する役割を持つすい臓が損壊する
ということが挙げられます。
2型糖尿病はインスリンの分泌量が不十分であること、働きが弱いことが原因で引き起こされます。
糖尿病を患った9割の方が2型糖尿病にあたります。
若い人の発症もありますが、2型糖尿病を患う患者の多くが40歳を過ぎたあたりから発症しています。
生活習慣の乱れや遺伝が発症の原因となっています。
主な症状は
- 疲労を感じる
- 手足が乾燥して痒くなったり、感覚が低下したり、チクチクした痛みが出てきたりする
- 感染症にかかりやすくなる
- 尿の回数が増える
- 目がかすむ
- 性機能に問題が出る
- 皮膚の傷が治りにくくなる
- 空腹感を感じやすくなる
- 喉が渇く
です。
初期の段階では自覚症状がなく、少しずつ症状が現れてきます。
2型糖尿病は
- 40歳以上の方
- 肥満体質の方
- 血縁に糖尿病の患者がいる方
- 運動不足の方
が患いやすいといえます。
2型糖尿病の発生は遺伝性の可能性があります。
そのため家族に糖尿病患者がいる方は糖尿病の検査をすることがオススメです。
適切な運動を行うことで糖尿病の発症を防いだり、遅らせたりすることができるのです。
痩せていても糖尿病を患う可能性がある
糖尿病は太っている人だけが患う病気ではありません。
痩せている人も同様に糖尿病を発症することがあります。
痩せている人は異所性脂肪がつきやすいという特徴があります。
異所性脂肪とは中性脂肪のひとつで、本来つくはずのない箇所に蓄積されてしまう脂肪のことです。
異所性脂肪が溜まってしまう主な原因は
- 運動不足
- 食べ過ぎによる過剰なカロリーの摂取
とされています。
仮に標準体重であっても体脂肪が多い人は糖尿病になる可能性があるのです。
また高齢者の場合は、筋肉内への脂肪の蓄積が起こってきます。
筋肉内への脂肪の蓄積はインスリンの働きを弱め、血糖がうまく取り込めないことから高血糖になっていくので注意が必要です。
糖尿病の恐ろしさは体重の減少だけではない
糖尿病には合併症があります。
合併症とはある病気が原因で発症する病気のことです。
糖尿病が原因で以下のような症状が引き起こされます。
- 糖尿病神経障害
- 糖尿病網膜症
- 糖尿病腎症
- 動脈硬化
それぞれどのような症状なのかを解説します。
糖尿病神経障害とは、高血糖が原因で手足の神経に異常をきたし、痺れや痛みを引き起こす病気のことです。
左右対称に痛みが現れ、慢性的な痛みに悩まされたり、病気が進行すると足潰瘍や足壊疽といった血行障害を伴う可能性があります。
糖尿病網膜症とは、血糖値が高いことが原因で目の中の網膜が損傷を受け、視力低下につながる病気のことです。
自覚症状がなく、進行に気づくのが遅れると失明に至ります。
早期発見が大切ですので、年に一度は瞳孔を特殊な目薬で開いて視神経や網膜といった構造を観察する眼底検査を行うようにしましょう。
糖尿病腎症とは、高血糖が原因で腎臓にある血管がむしばまれる病気のことです。
自覚症状がないまま進行し、腎臓の機能が失われてしまうと透析治療が必要になります。
透析治療とは全身の血液を体外に排出し、透析器と呼ばれる機械を通すことで血液をろ過して、綺麗になった血液を再度自分の体に戻すという治療方法です。
透析治療は1日から2日おきに病院へ行き、約5時間ほどかけて行われます。
動脈硬化とは、動脈と呼ばれる血管の内側にプラークという細菌の塊が付着し、溜まることで血管の弾性がなくなりもろくなっていく状態を指します。
溜まったプラークが破裂することで血栓と呼ばれる血液の塊が流れ出し、血管を詰まらせてしまいます。
その結果、心臓病や脳卒中といった後遺症を残したり、命に関わる病気を引き起こすのです。
自覚症状がないまま合併症が進行していた場合、日常生活に支障をきたす可能性があります。
糖尿病により合併症が引き起こされると足の切断や失明、人工透析や命に関わる事態を招きかねません。
早期対応できるよう定期検診を行うようにしましょう。
糖尿病患者が増えている?糖尿病の実態とは
平成28年に厚生労働省が行なった調査によると「糖尿病が強く疑われる者」は約1000万人いるといわれています。
この糖尿病患者が増加する背景には以下のような原因が考えられます。
- 食習慣の変化
- 運動不足
欧米のジャンクフードやファストフードが日本でも日常で食べるようになりました。
このような高カロリーな欧米食は内臓脂肪を蓄積させやすいという特徴があります。
また内臓脂肪はすい臓で生成されるインスリンの働きを弱めてしまいます。
もともとインスリンの分泌量が欧米人と比べ少ない日本人は、そこに運動不足が重なることで血糖が一定の幅を超えてしまい、糖尿病を引き起こすのです。
糖尿病で体重が減少。どのように対応すればよいのか
糖尿病を改善するためには生活習慣を見直さなければなりません。
改善方法は主に2つです。
- 食習慣の改善
- 運動不足の解消
まずは食習慣の改善から解説していきます。
糖尿病の人が気をつけたい食習慣は5つ。
- 肉の脂身や揚げ物、ケーキなど脂肪や飽和脂肪、トランス脂肪を減らす。
- おやつやジュースといった砂糖を多く含む食品の摂取を制限する。
- 全粒粉パンや玄米から食物繊維の摂取量を増やす。
- 果物野菜の摂取量を増やす。
- 禁酒する
ジュースには多量の糖質を含んでいますので、喉が渇いた際にはジュースではなく水やコーヒー、紅茶を飲むようにしましょう。
また、アルコール類はすい臓のインスリンの分泌を妨げます。
糖尿病を患っている方は禁酒しましょう。
食べるものに関しては、野菜の摂取量を増やし、全粒粉パンや玄米から食物繊維を摂取。
天ぷらやマヨネーズといった油脂類を避け、塩分は1日10グラムまでにしましょう。高血圧の方は合併症の危険性もあるため1日6グラムまでとされています。
次に運動不足の解消についてです。
インスリン運動不足を解消することにはさまざまなメリットがあります。
- インスリン製剤の効きがよくなる
- 標準体重まで減量することでインスリンの働きが活性化する
- 血圧や脂質の値が下がることで血管合併症のリスクを抑える
インスリン製剤はインスリンの分泌が少ない、もしくは全くない方が使用する注射剤です。
インスリン製剤を自己注射し、健康な状態の血糖値に近づけます。
これをインスリン療法といいます。
次に運動不足の解消方法について紹介します。
まずは自分自身の標準体重を確認しましょう。
標準体重は身長(メートル)×身長(メートル)×22で求めることができます。
ここで求められた標準体重を目標に運動および運動による減量を行いましょう。
ひとまずは2,3ヶ月後に体重の5%減量を目標にするとよいです。
運動方法についてですが、気軽に取り組めるウォーキングがオススメです。
無理のない程度でウォーキングを行い、毎日継続して取り組みましょう。
適度な運動は健康促進のために良いのですが、以下の方は運動方法を事前に病院の先生に相談しましょう。
- 血糖や血圧のコントロールが著しく不良の方
- 熱がある方
- 足に傷がある方
- 糖尿病腎症、糖尿病網膜症、糖尿病神経障害といった3大合併症を患っている方
- BMI30以上の高度肥満の方
- 狭心症、陳旧性心筋梗塞、末梢動脈閉塞のある方
- 上記に関する疑いがある方
上記で説明しているBMIとは肥満指数と呼ばれるもので肥満の目安を表す数値です。
BMI値は、体重(kg)×身長(m)×身長(m)で求められます。
BMI値22が最も病気になりにくいと言われています。
運動中や運動後は血糖値が低下します。
血糖値を下げたり、血糖値の上がりすぎを抑制するインスリン製剤を使っている方は、急激な血糖値の低下に注意が必要です。
糖尿病は治すのではなく抑え込む病気
糖尿病は治すのではなく、抑え込む病気といわれています。
抑え込むとは、治療を続けることで血糖値を正常に近い状態に保ち、健康な人と同様の生活できるようにすることです。
具体的には
- 毎日、適度な運動を行う
- 食習慣を改める
- 状況に応じて薬物療法を行い、血糖値、体重、血圧、脂質を適正に保つ
- 定期検診を行い、その結果に応じた治療を行う
ということです。
糖尿病を抑え込むためには血糖値以外にも気にすべきことがあることを知っておきましょう。
まとめ
急激な体重の減少が糖尿病の症状のひとつであることがお分かりいただけたかと思います。
上記でお伝えしたことをまとめると
・糖尿病が原因で体重が減少するのは、すい臓で分泌されるインスリンの働きが悪くなったもしくは分泌されなくなったから
・痩せている人でも糖尿病を患う可能性がある
・糖尿病には1型糖尿病と2型糖尿病がある
・糖尿病が恐ろしいのは、放っておくことで合併症を引き起こし、手足や目、腎臓に大きな障害を負ってしまうこと
・糖尿病患者が増えているのは生活習慣の乱れが主な原因
・糖尿病を患ったら食事療法、運動療法、薬物療法で対応
です。
いずれにしても早期発見と適切な治療を行うことが大切です。
尿の回数が多い、喉が渇きやすい、急激に体重が減少したと感じたら一刻も早く病院に検査を受けにいきましょう。
この記事の監修ドクター
アメリカ、カナダ、ブラジルの3カ国で認定された国際免許を取得している自然療法専門医。
スコッツ先生のプロフィール

























