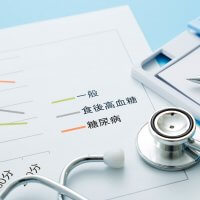目次
糖尿病と咳に関する基礎知識
弊社の商品開発チームの医師監修
Q. 糖尿病と咳にはどのような関係がある?
A. 糖尿病によって免疫力が下がり、感染症にかかりやすくなります。その結果、咳や疲れ、痰などの症状を感じるのです。

糖尿病と咳にはどのような関係がある?
糖尿病は、さまざまな不調を引き起こします。その症状の1つに咳が挙げられ、ただの咳と思っていても深刻な状態を招く恐れがあるため注意が必要です。
咳が長引く、空咳が続くといった症状が見られる場合、糖尿病により感染症を併発している恐れがあります。感染症にはさまざまな種類があり、風邪やインフルエンザから水虫、歯周病など身近な病気もたくさん存在します。
糖尿病の方が、咳が少し気になるというときは、このような感染症にかかっていないかを確認する必要があります。感染症にかかりやすくなる原因としては、糖尿病によって血糖値の高い状態が続き、免疫細胞に影響を及ぼすからです。病原菌としっかり戦うことができず、病気が進行してしまいます。
さらに、糖尿病が進行すると血行障害や神経障害になる確率も高まります。その結果、感染症が悪化し、治療に時間がかかる場合もあるのです。
ただの咳と思わず、気になる症状が見られたら早めに病院へ行きましょう。
咳に関する具体的な症状
前述した通り、糖尿病により感染症のリスクが上昇すると咳も発生しやすくなります。では、具体的にはどのような咳が出る場合、注意が必要なのでしょうか?ここでは、咳の症状について紹介します。
・空咳が続いている
・咳が2週間以上治らない
・色の濃い痰が出ることもある
このような症状が見られるときは病気が隠れているサインと思って良いでしょう。
糖尿病を患っていることで免疫力が弱まり様々な病気にかかりやすくなっているということが考えられます。いつもとは違う、嫌な咳が続いている場合は、早めに病院で診てもらいましょう。糖尿病を患っていると、気管支の病気も悪化しやすいです。
咳が止まらないのはなぜ?
 糖尿病患者では咳が2週間以上続くという場合、ただ風邪が長引いているというよりは百日咳などの感染症にかかっている可能性が高いです。
糖尿病患者では咳が2週間以上続くという場合、ただ風邪が長引いているというよりは百日咳などの感染症にかかっている可能性が高いです。
また糖尿病を発症していることで、さらに咳が長引く恐れもあります。健康な人であれば治まっているはずの期間が経っても、糖尿病患者は症状が続いているということも多いです。いつまでも咳が止まらない、仕事にも支障が出るというときは、早めにかかりつけ医に相談しましょう。
風邪から気管支炎や喘息になっている可能性もあります。鼻水が原因で、後鼻漏を発症している場合もあるため、ただの咳と過信せず用心しましょう。
こんな咳には要注意
普段何気なくすることの多い咳ですが、糖尿病患者の場合は症状が長引いたり、他の病気の引き金になったりすることがあります。そこで、以下のような咳には気をつけましょう。当てはまる症状があったら、早めに病院で診てもらいましょう。
・咳や痰が長く続き、よくならない
・血痰が出る
咳や痰がよくなるどころかひどくなっている、薬を飲んでも効果が見られないなど、一向に症状が改善されない場合、重篤な病気が隠れている可能性があります。百日咳にかかる人が多くなっていますが、結核のリスクも潜んでいます。また、風邪やインフルエンザ以外に、逆流性食道炎を引き起こしている可能性もあるため、自身の体調には敏感になっておきましょう。
ただし病気が関係していないこともあります。工場から出る排煙や車から出る排気ガス、喫煙の際の煙などによって咳が続くこともあるのです。日々の生活の中に咳のリスクは潜んでいることを理解しておきましょう。
糖尿病の際は感染症を予防することが大切
糖尿病患者は感染症のリスクが高まるため、予防対策をとることは大変重要となります。下記の方法で対策を取りましょう。
血糖コントロール
糖尿病の合併症である神経障害や血流障害が感染症を招き咳を引き起こします。そのため咳が気になる場合には、まずは血糖コントロールを適切に行うようにしましょう。
血糖コントロールを適切に行うには、糖尿病の根本的な治療法である食事と運動を基本とします。そのうえで、薬物療法を用いながら、経過を観察するというケースが多くなります。ひとりひとりの糖尿病の状態に合わせて適した方法で負担を感じずに続けられる方法がベストです。食事内容や食事量、食べ方のコツ、適度な運動方法などにおいて医師からアドバイスをうけることもできます。
適切な血糖コントロールを続けていくためには、毎日血糖値を測定することも大切です。食事や運動前後の血糖値を書き留めておくことで、自身の血糖値の変わり方を確認できます。どんなときに血糖値が上がりやすいのか、どんな生活が糖尿病に悪影響を与えているのかを把握できるでしょう。
体調管理
冬に流行することの多い感染症を予防するためには、日々のケアも重要です。糖尿病を患っている人は、年中感染症にかからないように注意する必要があります。マスクの着用やうがい、手洗いは必ず行ないましょう。外出から帰ってきたら、まずはマスクを外し、うがい手洗いを行ないましょう。日課にするだけでも、感染症のリスクを下げられます。
また、咳の症状をはじめ様々な不調で悩まないために、日々の睡眠はしっかり取っておきましょう。睡眠不足の状態が続くと、糖尿病の治療で重要となる血糖コントロールもうまくいかなくなります。規則正しい生活を心がけるためにも、質の良い睡眠は必須です。日付が変わるまでに布団に入る、寝る前に電子機器を見るのは控える、入浴は早めに済ませておくなどの方法を取り、質の良い睡眠につなげましょう。しっかり眠れると、翌朝すっきりと目覚めることができます。疲れを感じずに1日のスタートを切れるため、有意義な時間を過ごせるでしょう。
睡眠に気をつけるのと同時に、ストレスを溜めないことも大切です。ストレスは、糖尿病の悪化やその他の病気の要因となります。日々ストレスを溜めている人は、適度に発散しましょう。趣味に没頭したり、気分転換に外出してみるなど、気分がリフレッシュできることを選ぶと良いです。
早めの受診
咳が気になるという段階で、早めに医師に相談するなどの対策を取ると安心です。咳以外の症状も現れているのに放置してしまったという事態は避けましょう。少しでもいつもと違う症状を感じたら、医師に相談すべきです。
そのためには、日ごろから自身の体調で異変が起きていないかも確認することが大切です。糖尿病では病気の発見が遅れる可能性があるため、足に異変が生じていないか、目の見え方には異常がないかなどこまめに確認しておきましょう。
自分自身で体調に気をつけるのと同時に、家族の協力も必要です。自分では気づかないことを、家族が先に発見してくれる可能性もあります。自分では気づかない点を、指摘してもらうことも可能です。
感染症についての理解を深めることも大切
糖尿病を発症していると、感染症にかかるリスクは高まります。
咳をはじめとした様々な症状が挙げられる感染症についての理解を深めておくことも大切です。どのような種類の感染症があるのか、どんな症状に気をつけるべきなのかといった点を中心に、感染症についての知識を得ておきましょう。
感染症に関する知識を得ておくことで、自身の身体で起きている異変にも早く気づくことができます。手遅れになる前に対処できるため、適切な治療を受ければ身体は回復していくでしょう。
糖尿病患者におすすめの予防接種
咳をはじめとした症状から感染症を悪化させないために、予防接種を受けておくことも大切です。糖尿病を患っていると、免疫力が低下しがちです。今まではなんともなかったことでも、治りが遅いと感じることが増えます。
以下の予防接種を受けておくと安心でしょう。
インフルエンザ
毎年、冬に大流行するインフルエンザ、糖尿病を患っていることで症状が悪化しがちです。特に65歳以上を過ぎている人や、心臓や呼吸器に持病がある人、免疫力が低下している人はシーズンが到来するまでに早めに予防接種を受けておきましょう
肺炎球菌
高齢者においてリスクが高まる肺炎は、血糖コントロールがきちんとできていないと症状が悪化しやすくなります。肺炎の治療を行なうために、入院が必要になるというパターンもあります。肺炎球菌のワクチンを摂取しておくと、感染症や肺炎の発症リスクを下げることが可能です。インフルエンザワクチンと同様、受けておきたい予防接種の1つです。特に高齢で糖尿病を患っている人は受けておきましょう。
咳をはじめとする感染症による不調の治療法は?
咳をはじめとする感染症による不調は、糖尿病を患っている人なら誰でも体験する可能性があります。では、感染症にかかった場合、病院ではどのような治療が行なわれるのでしょうか?
薬を使った治療法が一般的
感染の部位や病原菌ごとに、適した薬を服用して改善を図ります。抗菌薬や抗真菌薬を用いることが多いです。しかし、感染症の影響によって血糖値のコントロールがうまくいかなくなると、感染症の状態が悪化する恐れがあります。そのため、まずは血糖管理から行うことが重要となります。感染症にかかっているから治療を行うのではなく、そもそもの血糖コントロールがきちんとできているかどうかを確認する必要があります。
糖尿病を発症していると、神経障害によって感染症の症状に気づきにくくなっていることがあります。痛みを感じないまま過ごしていて、病気が進行してしまったというケースもあるため、根本的な糖尿病の治療を同時に行なうことが最も大切なのです。
定期的に検診を受けて早期発見につなげよう
糖尿病を患っていると、恐ろしい感染症にかかるリスクが高まってしまいます。そのため、定期的に医師の診察も受けることも大切です。月に1度など定期的に病院で診てもらっておくと、糖尿病や感染症以外の病気を発見することにもつながります。糖尿病を患っていても、いつまでも健康的に過ごすため検診はきちんと受けましょう。
まとめ
咳は、誰でも体験したことのある症状の1つでしょう。咳といえば、風邪やインフルエンザ、アレルギー性鼻炎などから起こることの多い症状ですが、糖尿病の場合には注意が必要です。免疫力が低下する関係で、さまざまな感染症にかかりやすくなっているからです。
咳の症状を注意して見ておきながら、どのような感染症があるのか、咳以外の症状としてはどんなものが挙げられるのかを確認しておきましょう。その上で、血糖コントロールを行ったり、睡眠やストレスとも上手に付き合いながら、感染症を防ぎましょう。