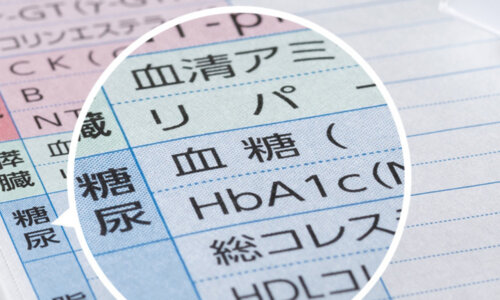目次
糖尿病の完治に関する基礎知識
弊社の商品開発チームの医師監修
Q. 糖尿病は一度発症すると完治しないって本当ですか?
A. 現代の医療では、糖尿病は完治しない疾患とされています。しかし、新薬の開発や研究によって近い将来「糖尿病を完治できる」といった時代が来る可能性はあるでしょう。
糖尿病は完治しない病気なの?
 現代医療において糖尿病は、一度発症すると完治しない病気とされています。これは、糖尿病患者さんの膵臓機能やインスリン分泌能力、インスリン抵抗性などが一旦壊れてしまうと、完全に元に戻すことが困難であるためです。
現代医療において糖尿病は、一度発症すると完治しない病気とされています。これは、糖尿病患者さんの膵臓機能やインスリン分泌能力、インスリン抵抗性などが一旦壊れてしまうと、完全に元に戻すことが困難であるためです。
そのため、糖尿病治療では完治を目指すのではなく、食事療法や運動療法によって高血糖を改善することが目的となります。糖尿病の治療は、原則的に「生涯にわたって継続する」というのが一般的です。
日本糖尿病学会が発行しているマニュアルでも、「医師は患者に対し、糖尿病が完治したと診断してはならない」といった方針が定められているといいます。
血糖値やヘモグロビンA1cの数値が改善したとしても、完治という言葉を使わず「改善」や「正常値」などの表現をします。
「改善しましたね」と医師から言われた際に、「糖尿病が完治したということですか?」と尋ねても「糖尿病の場合には、完治とはいえないんですよ」といった答えが返ってくることでしょう。
また、糖尿病は一時的な病気というよりは、「高血糖になりやすい体質」と捉えるべきです。食事療法や運動療法、薬物療法によって一時的に数値が改善されても、元の食生活や運動量に戻してしまうと再び血糖値が上昇します。
血糖降下薬やインスリン注射を行っている患者さんが、「糖尿病が完治した」と思い込んで薬物療法を中止すると、ほとんどの方が高血糖状態に戻ってしまうのです。
しかし、糖尿病の初期段階で発見できた場合には、例外もあります。薬やインスリン注射の力を借りて、少しの間だけ膵臓に休息を与えることで、再びインスリン分泌機能が回復してくることもあるといわれています。
特に、肥満や内臓脂肪がある患者さんでは、食事や運動によって減量に成功するとインスリン抵抗性が正常になったり、血糖値が改善されたりすることも少なくありません。
早期発見・早期治療を開始した糖尿病患者さんや、厳格な血糖コントロールを実践できた人では、医師から「糖尿病が完治した」と診断されなくても、血糖値やヘモグロビンA1cが安定していれば、実質的には健康な人と同じ状態で生活することも可能だといいます。
糖尿病を完治した人がいるって本当?
最近では、ネットのブログやSNSなどで糖尿病の治療過程や検査結果などを公開している患者さんも少なくありません。さまざまな情報を調査していると、「糖尿病が完治した」「血糖値が正常に戻って、糖尿病が治った」などの声に出会うことがあるでしょう。
しかし前述した通り、医師から「あなたは糖尿病が完治しましたよ」と診断されることはありません。そのため、「糖尿病が完治した」と発信している人の多くは、血糖値やヘモグロビンA1cの数値をもとに自己判断しているだけだといえます。
その証拠に、「医師から糖尿病が完治したと正式に診断されました」と話す人は、どこにもいません。
注意して欲しいのは、ヘモグロビンA1cが正常値になったからといって、糖尿病合併症の可能性はゼロではないという点です。
ある糖尿病患者さんでは、血糖値やヘモグロビンA1cが正常になっているにも関わらず、合併症のステージを調べるための検査を行ったところ、「尿アルブミン値」が6400もあったというのです。ちなみに、尿アルブミン値の正常値は18以下といわれており、6400は、即人工透析が必要なレベルです。
このように、血糖値やヘモグロビンA1cなどの「一部の数値」が改善されていても、重篤な糖尿病合併症が隠れていることは珍しくありません。特定の検査結果だけをもとに「糖尿病が完治した」と素人判断するのは、大変危険だといえるでしょう。
また、ブログなどで「糖尿病が完治した」と発信している人でも、最近の記事更新や経過報告がされていない場合には、現在再び糖尿病が悪化している可能性も否定できません。
最近は、インターネットで個人が自由に情報を発信できる時代となりましたが、すべての情報を鵜呑みにしないよう注意しましょう。
肥満を解消すれば糖尿病は完治する可能性あり?
2型糖尿病治療を10年以上継続している患者さんでも、肥満を解消すると「糖尿病が完治した」といえる状態まで改善できることが、ある研究によって判明しました。
これは、2017年にアメリカのニューカッスル大学のロイ・テーラー教授が、欧州糖尿病学会で発表したものです。
40年以上にも渡る調査では、肥満傾向がある2型糖尿病の患者さんが適切な食事療法で食事量をコントロールすると、肝臓の脂肪蓄積が7日間で大きく低下し、血糖値やインスリン抵抗性が正常化することがわかりました。
さらに8週間継続した場合には、膵臓に溜まった内臓脂肪が減少して「インスリン分泌機能」も改善したといいます。
糖尿病は、膵臓からのインスリン分泌がスムーズに行われなくなり、食後の血糖値を下げることが困難となる病気です。このインスリン分泌は、膵臓に内臓脂肪が蓄積することでも機能が低下します。
体重や内臓脂肪を減少させるための食事療法・運動療法を正しく実践すると、膵臓にこびりついた脂肪も減り、再びインスリン分泌機能が回復するというので見逃せません。
具体的には、6~12か月をかけてゆっくりと体重を落とすことが推奨されています。
目安としては、脂肪肝がある患者さんの場合、体重の7~10%程度を1年かけて減量するイメージです。運動は、1日30分程度のウォーキング(有酸素運動)が良いとされています。特に、食後1~2時間以内に行うと効果的でしょう。
糖尿病患者さんに限らず、ダイエットをする際には「極端な食事制限」は良くありません。身体が飢餓状態を察知すると、筋肉からエネルギー源が放出され始めます。すると、筋肉量が低下してしまい「基礎代謝」が落ちてしまうのです。
基礎代謝が落ちると、毎日の消費エネルギー量が減少するため、肝臓に脂肪が蓄積しやすくなるといいます。
低カロリー・低脂質の食事を徹底的に心がけ、適度な有酸素運動を取り入れながら「内臓脂肪」を落としていくことで、インスリンを産生する膵臓のβ細胞の働きが回復します。
医師から肥満気味だといわれている糖尿病患者さんにとっては、この研究結果は大きな希望となるのではないでしょうか。
糖尿病の完治とまでいかなくとも、病状を改善したり、正常な血糖値をキープすることは、重篤な「糖尿病合併症」の予防にもつながるといわれているため、注目したい治療法のひとつです。
糖尿病の完治を調べる検査方法は?
前述した通り、糖尿病は医師から「完治」を告げられることはない病気です。しかし、検査結果によっては事実的に寛解したと判断できるケースもあります。
ちなみに、「寛解」とは症状が一時的に消えたり落ち着いた状態のことを指しますが、糖尿病の場合には再発の恐れが高いため、医師がこの言葉を使う場面はほとんどないでしょう。
糖尿病治療においては、糖代謝が健康な人と同じ状態になったことを確認するために、「75gブドウ糖負荷試験」を行うのが一般的です。
検査方法は、10時間以上の絶食をした後に75gのブドウ糖を水に溶かしたものを飲み、その後2時間の血糖値推移を測定するものですが、2時間値が140mg/dL未満になれば正常とみなされます。
また、この「75gブドウ糖負荷試験」で2時間後の値が200mg/dL以上となったときには、糖尿病であると診断されます。
繰り返しになりますが、特定の検査を行っただけでは「糖尿病が完治した」とは言い切れません。空腹時血糖値や、尿アルブミン値、ヘモグロビンA1cなどさまざまな項目をクリアする必要があるのです。
そして、その数値を長期間キープすることが何よりも大切になってきます。糖尿病患者さんの多くは、一度正常値が確認されると油断をして、もとの乱れた食生活や運動不足に戻ってしまう傾向があります。
せっかく正常値になっても、血糖値が上がりやすい体質自体は改善されていないため、すぐに数値が悪化してしまうことも少なくありません。
検査結果が正常だったからといって、食事療法や運動療法を中止せず、健康的な生活習慣を心がけるようにしてください。
ためしてガッテンで紹介された糖尿病の完治方法とは?

2011年に放送されたNHKの「ためしてガッテン」という番組内では、糖尿病の完治方法について解説され、多くの糖尿病患者さんから注目されました。
ためしてガッテンで放送された内容は、早期にインスリン注射を用いることで膵臓のβ細胞を十分に休息させてから、インスリン分泌の働きを蘇らせるというものです。
糖尿病は、膵臓のβ細胞がダメージを受けてインスリン放出を行わなくなってしまう病気です。そのため、食事療法や運動療法を行っても「血糖値」の改善がみられない場合には、血糖降下薬やインスリン注射などの薬物療法を実施するのが一般的といわれています。
ためしてガッテンで紹介された「糖尿病完治方法」は、β細胞が完全に死滅する前の初期段階からインスリン注射を1日4回行うことで、数週間程度で膵臓機能を完全に回復させることが可能になるいう内容でした。
糖尿病患者さんの中には「インスリン注射を開始すると、一生続けなければならないのでは?」と勘違いしている方も少なくありません。しかし、膵臓のインスリン分泌機能が少しでも残っている場合には「一時的な糖尿病治療」として行われることもあるのです。
β細胞の働きが復活してくれば、血糖降下薬やインスリン注射などの薬物療法を中止できる場合も多いといいます。
糖尿病の早期段階では、「まだインスリン注射はしなくない」と拒む患者さんもいます。しかし、糖尿病が重度に進行してから開始するより、早めの対策としてスタートした方が良いとされているのです。
もちろん、インスリン注射を1日4回行うだけでは糖尿病を改善することはできません。適切な食事療法と運動療法をあわせて実践しながら、良好な血糖コントロールを保つ努力を怠ってはいけません。
糖尿病を発症して6年以内なら完治する可能性が判明
肥満や内臓脂肪がある糖尿病患者さんの場合には、糖尿病を発症してから6年以内であれば完治する可能性が判明したといいます。
これは、英国で行われている「DiRECT」(糖尿病を寛解するための臨床試験)でわかったものです。調査には298人の2型糖尿病患者が参加し、徹底した低カロリー食とウォーキングなどの有酸素運動を毎日行いました。
その結果、肥満のある患者さんの多くが、体重を減らして肥満を解消することによって「糖尿病を発症する前の状態」に戻せたというのです。
特に、糖尿病に罹患してから6年以内の人は、食事や運動などの生活スタイルをしっかりと見直すことで、肝臓や膵臓の「内臓脂肪」が減少し、β細胞の再起動・再生が可能となると発表されました。
膵臓のβ細胞が再起動・再生するというのは、これまで広くいわれてきた「糖尿病は一度発症すると完治できない病気」といった説を大きく覆すものであり、さまざまな方面から注目を集めています。
生活スタイルの改善は、高い意識と強い意志を持っていれば誰でも実行可能な治療法です。これらの研究結果を、実際の糖尿病治療に適用するため、現在も研究が続けられているといいます。
糖尿病を完治する新薬登場に期待がかかる
糖尿病は、膵臓のβ細胞が減少したり破壊されたりして、インスリン分泌が正常に行われなくなる病気です。そのため、糖尿病患者さんの薬物療法では、インスリン注射をはじめ、血糖値を低下させる働きのある薬や、インスリンの効きを良くするための薬が用いられてきました。
これらの薬物療法では糖尿病を根本的に完治させることはできません。一時的にインスリンを与えたり、血糖値を低下させる効果しか見込めないといいます。
しかし、最近では「インスリン」の分泌に大きく関わる、膵臓のβ細胞自体を増殖させる治療薬の開発が進んでいるのです。これは、アメリカのマウントサイナイ医科大学の研究チームが行ったもので、私たち人間の身体にもとから備わっているβ細胞を増やし、インスリン産生能力を回復させる「新しい糖尿病治療」につながるといいます。
糖尿病は、インスリン分泌が減少して高血糖状態が続く疾患ですが、逆にインスリンが異常に分泌されてしまう「インスリノーマ」と呼ばれる病気も存在します。研究チームが注目したのは、このインスリノーマのメカニズムです。
インスリノーマでは、特定の遺伝子レシピが大きく関わり膵臓に腫瘍ができて「β細胞」をどんどん増殖していきます。これと似たような働きを起こすのが「ハルミン」という成分です。
ハルミンは、南米のアマゾン川流域に生息する「アヤワスカブドウ」に含まれており、人間のβ細胞を増殖・活性させる働きがあるといわれています。しかし、ハルミン単体ではβ細胞の増殖率が低く、糖尿病を完治させるほどの力はありません。
そこで研究チームが行ったのは、「DYRK1A阻害剤(二重特異性チロシン調節キナーゼ1A)」と「TGFβSF阻害剤(ベータ型変異増殖因子スーパーファミリー)」と呼ばれる薬剤をハルミンと組み合わせることで、β細胞の急速な増殖を促すというものです。
これにより、1型糖尿病と2型糖尿病患者さんのβ細胞を再生させ、インスリン分泌を回復させる新たな治療法が確立される可能性が高いといいます。
ただし、新薬自体は開発されましたが「膵臓だけに届ける方法」がまだ見つかっていないため、糖尿病治療の現場で活躍するのはもう少し先になるかもしれません。しかし、近い将来「糖尿病は完治できる」といった時代が来るはずです。
まとめ

糖尿病は、現在の医学では「完治しない疾患」とされています。しかし、食事療法や運動療法を正しく実践すれば、良好な血糖コントロールを長期間保つことは可能です。
医師から「糖尿病が完治した」と診断されなくても、実質的には正常な人と同じレベルの生活を送れるようになります。
しかし、いくら血糖値やヘモグロビンA1cなどの数値が正常になったからといって、油断しないようにしましょう。元通りの乱れた食生活や運動不足の日々を過ごしていると、再び血糖値が高くなりやすいことを忘れてはいけません。
この記事の監修ドクター
アメリカ、カナダ、ブラジルの3カ国で認定された国際免許を取得している自然療法専門医。
スコッツ先生のプロフィール