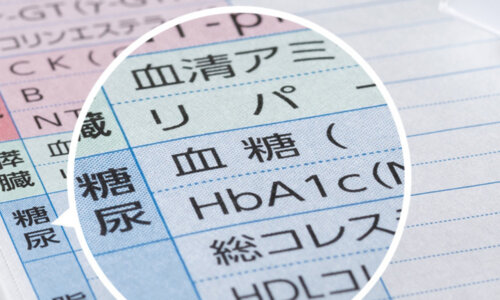目次
糖尿病と白米に関する基礎知識
弊社の商品開発チームの医師監修
Q. 糖尿病で治療中、1回の食事で摂取して良い白米(ご飯)の量はどれくらいですか?
A. 糖尿病患者さんの年齢や体重、性別、活動量によって異なりますが、1日1600キロカロリーの方なら1回の食事あたり150g(240キロカロリー)のご飯(白米)を目標にしてください。
糖尿病のご飯で注意すべきこと
 糖尿病と診断された患者さんは、健康な人と比較して血糖値が高くなりやすいため、食事療法と運動療法によって良好な血糖コントロールを行う必要があります。
糖尿病と診断された患者さんは、健康な人と比較して血糖値が高くなりやすいため、食事療法と運動療法によって良好な血糖コントロールを行う必要があります。
しかし、いざ糖尿病の食事療法を始めようと思っても「どんなご飯を食べれば良いのか」「ご飯の量は、どの程度減らすべきなのか」など、さまざまな不安や悩みがつきまとうことでしょう。
特に、白米をはじめとした「ご飯」は糖質量が多く、血糖値を急激に上昇させる食品として、毎日の摂取量を減らすように指導されることがほとんどです。
日本人の食事では、精製された白米を主食とすることが当たり前になっているため、糖尿病の治療を開始するまでは「ご飯の量について、さほど考えていなかった」「ご飯は毎食必ずおかわりしていた」という方も少なくありません。
ところが、糖尿病を発症した患者さんの場合、これまでと同様の食生活を続けていては危険です。高血糖をはじめ、肥満や高血圧の原因となり、網膜症、神経障害、腎症合併症などのリスクが高まるため注意しましょう。
白米などのご飯は、お茶碗に半分~軽く1杯程度までを限度とし、その他のおかずでバランスよく栄養素を摂取するようにしてください。糖尿病の食事療法では、炭水化物、脂質、たんぱく質といった三大栄養素はもちろんのこと、野菜や果物に含まれるビタミン、ミネラルなどもしっかりと摂ることが大切です。
ご飯を減らすと、満腹感を得るためにさまざまな種類のおかずを口にすることとなるでしょう。もちろん、せっかくご飯を減らしても「おかず」の食べ過ぎでカロリーオーバーしてしまっては意味がありません。
1日の摂取目安カロリーは、年齢や性別、体重などによって変動します。医師から指定されたエネルギー摂取量のなかで、栄養が偏らないように食品を選ぶ習慣をつけましょう。
カロリー管理や摂取栄養素のバランスをとるためには、日本糖尿病学会が発行している「糖尿病食事療法のための食品交換表」が便利です。
詳しくは、「糖尿病食事療法で推奨されているご飯の量は?」の項で後述します。
白米などのご飯で糖尿病リスクが高まるって本当?
日本国内や海外での研究では、日本人の白米摂取と糖尿病発症リスクについての関連が指摘されています。ご飯を多く食べている人は、将来糖尿病になりやすいというのです。
私たち人間が生きていくうえで必要となる「三大栄養素」は、炭水化物、たんぱく質、脂質ですが、このうちの炭水化物を摂取すると血糖が上昇しやすくなります。
これは、炭水化物に含まれている糖が原因です。
日本人が1日に摂取する炭水化物量の平均は、男性が287g、女性では233gといわれています。主な炭水化物の摂取源は、ご飯(白米)です。
一般的な和食では120~180g、日本人が好むカレーや丼ものでは1食につき200~260gものご飯を食べているといわれています。最近では、牛丼の大盛りや特盛なども良く目にしますが、これらの白米量は360gにもなるので注意しなければなりません。
特に、女性の場合には1日のご飯摂取量が増えるごとに、糖尿病リスクが顕著に高まることがわかっています。
ある研究調査では、米飯の1日摂取量が165g(お茶碗1杯強)のグループに比べて、1日に420g(お茶碗3杯)食べているグループは糖尿病発症リスクが1.48倍になり、1日560g(お茶碗4杯)のグループでは1.65倍にも上昇したというのです。
もちろん、活動量が多い人では糖代謝や血糖上昇抑制効果が働くため、同じ量のご飯を食べていても糖尿病リスクはさほど上がりませんでした。
これらのことから、白米などのご飯を多く摂取しており、さらに運動不足の傾向がある女性は糖尿病になりやすいといえるでしょう。
白米は、精製するときに食物繊維やミネラルが失われます。そのため、腸内での糖吸収が早くなり、食後血糖値を急上昇させてしまうのです。
「ご飯は大好きだけど、糖尿病リスクは下げたい」という人は、毎日1時間程度の運動を取り入れ、お米を炊くときには雑穀や押し麦などをブレンドするようにすると良いでしょう。雑穀や押し麦には、豊富な食物繊維が含まれているため、糖の吸収を穏やかにして食後血糖値の上昇を抑える働きが期待されています。
糖尿病患者がご飯を食べ過ぎるとどうなるの?
 糖尿病治療では、食事療法によるカロリーコントロールが必須となります。これは、糖尿病を悪化させる要因として、患者さん自身の肥満、内臓脂肪などが大きく関わっているためです。
糖尿病治療では、食事療法によるカロリーコントロールが必須となります。これは、糖尿病を悪化させる要因として、患者さん自身の肥満、内臓脂肪などが大きく関わっているためです。
ご飯を食べ過ぎると、体重や内臓脂肪の増加に直結します。その結果、インスリン抵抗性がさらに高まってインスリンの効きが悪くなったり、膵臓からのインスリン分泌量が減少したりすることも珍しくありません。
また、1回の食事で大量の糖質を摂取すると、血糖値を下げる働きを持つ「インスリン分泌」が追い付かなくなり、高血糖になってしまいます。糖尿病患者さんの高血糖が続くと、血管に大きなダメージを与えて「動脈硬化」や「心筋梗塞」といった心疾患系の合併症を起こしやすくなるといわれており、注意が必要です。
万が一、「今回の食事ではちょっとご飯を食べ過ぎてしまったかな」と思った際には、食後にウォーキングなどの運動を多めに取り入れるようにしましょう。また、他の食事で摂取するカロリーを控えめにして、1日全体での摂取エネルギー量を調整することも有効です。
もちろん、これらの対処をすれば「ご飯を食べ過ぎても良い」というわけではありません。
特に、糖質の多い米飯を一度に大量摂取すれば、良好な血糖コントロールを保てなくなってしまいます。
網膜症や神経障害、腎症などの重篤な糖尿病合併症を発症する患者さんの多くは、「たまに食べ過ぎるくらいは大丈夫だろう」「次の食事でご飯を減らせば問題ないだろう」と、自分に甘い人が多くみられます。
しかし、血糖値の急激な上昇は、確実に患者さん自身の身体を蝕んでいることを忘れてはいけません。
糖尿病食事療法で推奨されているご飯の量は?
糖尿病患者さんの食事療法では、医師から指導された「1日の摂取カロリー」のなかで、さまざまな食品や栄養素を摂ることが基本です。
前述した通り、1日あたりの摂取エネルギー量は、性別、年齢、体重、活動量などによっても異なるため、「糖尿病なら、ご飯(白米)の量は何gにするべき」と明確には答えられません。
ただし、1日の摂取目安カロリーさえわかっていれば、「糖尿病食事療法のための食品交換表」によって、ご飯の量を計算することは可能です。食品交換表では、80キロカロリーを1単位として、表1から表6までの食品をバランスよく食べることが推奨されています。
白米は、表1の「穀類、いも、豆」に分類されており、50gが1単位となっています。
例えば、1日1600キロカロリーの献立例では、1回の主食量(ご飯の量)は150gで240キロカロリーが目安です。食事交換表の単位にすると、「3単位分」ということになります。
主食がご飯ではなく食パンの場合には90g、うどんなら240g、スパゲティーであれば60gを目標としてコントロールしましょう。
ちなみに、食パン90gは8枚切りが2枚程度の量です。また、スパゲティーは一般的に1人前が100gとされていますが、糖尿病患者さんの場合には6割程度まで減らすようにしてください。
ご飯を食べない「糖質制限」で糖尿病は治るの?
最近では、糖尿病の食事療法をはじめ、ダイエットなどでも糖質制限が注目されています。糖質制限は、字のごとく「糖質を含む食品を制限する食事法」のことです。
実際に、「糖質制限を始めてから、血糖値やヘモグロビンA1cが改善された」という糖尿病患者さんは多くいます。
しかし、現代の医療では「糖尿病は完治しない病気」とされており、糖質制限をしたからといって糖尿病自体が完全に治るわけではありません。この点は、しっかりと押さえておきましょう。
また、糖質が多いご飯(白米)を完全にカットして、野菜やキノコ類などの低カロリー・低糖質食品ばかり食べてしまう人も少なくありませんが、これは栄養バランスの乱れにつながるため避けてください。
前述した通り、私たち人間が生きていくうえでは、炭水化物、脂質、たんぱく質といった三大栄養素が必須です。糖尿病だからといって、糖質を減らすことばかりに気を取られていると、エネルギー不足になってしまいます。
もちろん、糖尿病患者さんのなかには、普段からご飯を食べ過ぎている方も多いので「炭水化物を減らそう」と努力することは糖尿病治療において大切です。
しかし、ご飯の量を極端に減らしてしまうと、食事後にお腹が空きやすくなる傾向があります。せっかく米飯から摂取する糖質量をカットしたのにも関わらず、間食で余計なカロリーや糖を摂取してしまう患者さんも珍しくありません。
 ご飯などの炭水化物は、確かに血糖値を上げやすい食品ではありますが、間食で手を伸ばしがちなスイーツや和菓子などの方が、よっぽど血糖コントロールを乱します。
ご飯などの炭水化物は、確かに血糖値を上げやすい食品ではありますが、間食で手を伸ばしがちなスイーツや和菓子などの方が、よっぽど血糖コントロールを乱します。
お米に含まれている糖は「複合糖質」と呼ばれており、何万個ものでんぷんや糖が組み合わさってできているため、消化や吸収に時間がかかるといわれています。
逆に、スイーツや和菓子に使われている砂糖は「単純糖質」なので、摂取してからすぐに血糖値を上昇させるのです。
糖尿病患者さんが糖質制限を行うときには、炭水化物の摂取量よりも砂糖自体の摂取量を減らすようにしましょう。コンビニや自動販売機で購入できる「ペットボトルジュース」や「清涼飲料水」にも、多くの砂糖やブドウ糖が含まれているため注意が必要です。
ご飯抜きなら糖尿病でもお菓子やお酒を摂取して良い?
糖尿病の食事療法を行っている患者さんでは、1日の摂取カロリーをしっかりと管理することが大切です。もちろん、患者さん自身も医師から食事内容やカロリー制限については指導をされているはずなので、「そんなの言われなくても知っているよ」といった方も多いでしょう。
しかし、食事療法に対する誤解があるのも事実です。特に多くみられるのは、「お菓子やケーキを食べたいから、ご飯を1回分抜く」「夜はお酒を飲みたいから、夕飯は食べない」といった患者さんです。1日の摂取カロリーさえ守っていれば、糖尿病は悪化しないと思い込んでいる方がときどきいます。
繰り返しになりますが、糖尿病の食事療法ではバランスの良い食生活を継続することが何よりも重要です。そのため、ご飯を抜いてまでお菓子を食べたり、お酒を飲んだりすることは絶対にしてはいけません。
お菓子やアルコールには多くのカロリーが含まれていますが、食事から摂取するような栄養素はほとんど入っていないのです。
さらに、インスリン注射や経口血糖降下薬を用いて薬物療法を行っている患者さんの場合には、ご飯を1回食べないだけで低血糖を起こしてしまうこともあります。
また、お酒に含まれるアルコールは、体内で分解されるときに糖とビタミンを消費するといわれており、夕食抜きでの飲酒は夜間低血糖を発症する恐れもあるため危険です。
妊娠糖尿病のご飯はどんなところに注意するべき?
 糖尿病のご飯について気にする方のなかには、妊娠糖尿病で悩んでいる女性も少なくありません。妊娠糖尿病とは、妊娠中に初めて認められた糖代謝の異常です。
糖尿病のご飯について気にする方のなかには、妊娠糖尿病で悩んでいる女性も少なくありません。妊娠糖尿病とは、妊娠中に初めて認められた糖代謝の異常です。
妊娠しているお母さんが高血糖だと、お腹のなかの赤ちゃんも高血糖になりやすく、心臓肥大や黄疸、巨大児、多血症などの合併症を起こしてしまう恐れもあるといわれています。
妊娠糖尿病だと診断された妊婦さんは、まずは食事療法による血糖コントロールを行うのが一般的です。目安としては、食前100mg/dL、食後2時間で120mg/dLをキープできるように管理しましょう。
ただし、お腹に赤ちゃんがいるときには母体も多くの栄養素を必要とします。そのため、極端なダイエットや食事制限は行いません。
食品から摂る糖が不足してしまうと、母体と赤ちゃんのエネルギーを産出するために、脂肪を分解してエネルギー源を補給しようと働きだしてしまうのです。このときに、ケトン体と呼ばれる物質が作られ、意識障害や昏睡などを引き起こす「糖尿病ケトアシドーシス」を発症してしまうことがあるため注意が必要です。
1日3食をバランスよく食べていても血糖値が改善されないときには、1日の摂取量を減らすのではなく「分割食」を取り入れます。
分割食は、1日5~6回程度の食事をこまめに摂ることで、1回分の食事量を減らして血糖値を安定させる食事法です。基本となる3回の食事にプラスして、間食を3回組み合わせます。間食は、約80~160キロカロリーを目安にして摂取しましょう。
牛乳やヨーグルトなどの乳製品をはじめ、手軽に食べることができる焼き芋、おにぎり、サンドイッチなどがおすすめです。
適切な分割食を実践しても、良好な血糖コントロールができない場合には、インスリン注射による薬物療法が行われます。インスリンは胎盤を通過しないため、お腹の赤ちゃんには影響がほとんどないといわれていますが、医師とよく話し合って治療法を決定していきましょう。
糖尿病治療中におすすめのご飯・パン
糖尿病の治療を行っている患者さんの多くは、「ご飯やパンなどの主食を満足に食べられない」と不満を持っているものです。しかし、糖尿病患者さんの血糖値を上げにくいご飯やパンも存在します。
日本人の主食といえば、精製された白米や小麦粉のパンが一般的ですが、茶色い主食を選ぶようにすると食後の血糖上昇を緩やかにしてくれるといいます。
具体的には、玄米、全粒粉入りのパンなどがおすすめです。これらの食品は「低GI食品」と呼ばれており、腸での糖吸収が遅く食後血糖値を上昇させにくいとされています。
これは、玄米や全粒粉などの「精製されていない穀類」は、胚芽に含まれる食物繊維、ミネラル、ビタミンが多く残っているためです。特に、食物繊維は糖の吸収や血糖上昇抑制に大きく関わっています。
また、白米の代わりに雑穀米を取り入れるのも良いでしょう。最近では、スーパーのお米コーナー付近には豊富な種類の雑穀米が並んでいます。プチプチとした食感は、食べ応えがあり、さらに普段よりよく噛んで食べる習慣がつくので、糖尿病患者さんの早食い防止にも最適でしょう。
まとめ
糖尿病と診断された患者さんは、適切な食事療法と運動療法によって、良好な血糖コントロールを行っていかなければなりません。しかし、糖尿病の食事療法は「食事制限」ではなく、私たち人間が健康に生活していくための「基本食」ともいえます。
白米などのご飯は目安量をしっかりと守り、さまざまな種類の食品からバランスよく栄養素を摂取するように心がけてください。
医師からの指導内容と、「糖尿病食事療法のための食品交換表」を最大限に活用しながら、毎日のご飯を楽しんで食べられるよう、できることから取り組んでいきましょう。