目次
糖尿病治療中のタンパク質摂取に関する基礎知識
弊社の商品開発チームの医師監修
Q. 糖尿病で食事療法を行っている場合のタンパク質摂取目安量は?
A. 体重1㎏あたり1.0~1.2g摂取するのが理想的です。体重50kgなら50~52gを目安としましょう。

糖尿病患者はタンパク質を制限するべき?
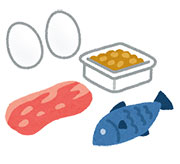 糖尿病治療を開始している患者さんは、日々の食事療法と運動療法、そして必要に応じた薬物療法によって、良好な血糖コントロールを行うことが不可欠です。
糖尿病治療を開始している患者さんは、日々の食事療法と運動療法、そして必要に応じた薬物療法によって、良好な血糖コントロールを行うことが不可欠です。
糖尿病食事療法では、食べてはいけない食品は特にありませんが、決められた1日の摂取エネルギー量の中でさまざまな栄養素・食品をバランスよく摂る必要があります。
摂取すべき栄養素は、タンパク質をはじめ、ビタミン、ミネラル、炭水化物、脂質などです。
その中でも、タンパク質は私たちの臓器、骨、筋肉を形成するために大切な栄養素のひとつです。糖尿病で食事療法を行っている患者さんの場合、1日の目安量は体重1㎏あたり1.0~1.2g摂取するのが理想的だといわれています。
タンパク質が不足すると、筋力の衰えや筋肉量の減少、下肢機能の低下につながってしまうため、運動療法の効率が悪くなる恐れがあるのです。
さらに、筋肉はブドウ糖の吸収・代謝を行う働きもあり、糖尿病患者さんの血糖コントロール・肥満予防には欠かせない臓器のひとつとして、注目されています。
偏った食生活でタンパク質が不足するのは大きな問題ですが、逆に過剰摂取にも注意をする必要があります。特に、三大合併症に分類される「糖尿病腎症」のリスクがある方や、すでに発症してしまった患者さんに関しては、タンパク質の摂取制限を指導されるのが一般的です。
タンパク質が体内で合成されるときにはアミノ酸が使われるのですが、そのうち余分なものは腎臓が尿にして排出します。しかし、腎臓自体が健康でないとスムーズに排出することができず、体内に蓄積してしまうのです。
また、余分なタンパク質は尿素などの老廃物に分解され、腎臓でろ過されます。このとき、あまりにも多い老廃物が発生すると、腎臓にも大きな負担をかけ、糖尿病腎症の進行を早めてしまうともいわれています。
さらに、血糖コントロールができていない糖尿病患者さんの場合、インスリンがタンパク質合成のサポートを上手くできなくなります。
摂取したタンパク質の栄養素を十分に活用することが難しくなると、本来使われるべき筋肉や臓器形成目的ではなく、「エネルギー源」として利用されてしまう現象が起こってしまうのです。
タンパク質は身体をつくるために重要な栄養素のひとつですが、糖尿病治療を開始している方の場合には、過剰摂取に注意が必要です。ご自身にとって適切な量をしっかりと把握しながら、バランスよく食事に取り入れていきましょう。
糖尿病なら肉より魚を食べる方が良い理由
 牛肉や豚肉の赤身肉をよく食べる人は、糖尿病リスクが高まるといった研究結果が発表されています。これは、シンガポールで実際に行われた研究で、45~74歳の6万3,000人の成人を対象として11年間も追跡調査されました。
牛肉や豚肉の赤身肉をよく食べる人は、糖尿病リスクが高まるといった研究結果が発表されています。これは、シンガポールで実際に行われた研究で、45~74歳の6万3,000人の成人を対象として11年間も追跡調査されました。
「赤身肉をよく食べるグループ」と「ほとんど赤身肉を食べないグループ」を比較したところ、糖尿病を発症するリスクに23%もの差が生じたといいます。
赤身肉には、動物性のタンパク質をはじめ、ビタミンB、亜鉛、鉄などの豊富な栄養素が含まれていますが、摂取しすぎると身体にあらゆる害をもたらすため注意が必要です。
肉に含まれる「ヘム鉄」は、体内の酸化ストレスや炎症を引き起こして、糖尿病患者のインスリン感受性を低下させるともいわれています。
「赤身肉にはタンパク質が豊富だから」と、食べ過ぎてしまうとヘム鉄の過剰摂取となり、膵臓でインスリン分泌を行うβ細胞に大きなダメージを与えてしまうこともわかっているのです。
また、赤身肉には飽和脂肪酸が多く含まれており、悪玉LDLコレステロール・中性脂肪を増加させ、心筋梗塞などの心疾患リスクを上昇させてしまいます。
さらに、焼肉やステーキなどの「こんがりと焼き目をつけたお肉」は、香ばしくて食欲をそそりますが、この焦げ目にはAGEと呼ばれる糖化最終産物が多いため、糖化ストレス亢進や動脈硬化の原因にもつながるので注意が必要です。
赤身肉を完全に禁止するわけではありませんが、糖尿病治療を行っている方のタンパク質摂取なら「肉より魚」が推奨されています。
肉が糖尿病リスクを上昇させるのに対し、魚は糖尿病リスクの低下が期待されている食品のひとつです。
特に、魚類に多く含まれているn-3系多価不飽和脂肪酸の一種である「エイコサペンタエン酸(EPA)」や「ドコサヘキサエン酸(DHA)」は、糖尿病患者のインスリン抵抗性やインスリン分泌を改善するといった報告もあがっています。
EPAやDHAは、サバ、アジ、イワシ、サンマなどの脂がのった魚に多く含まれているため、積極的に食生活へ取り入れると良いでしょう。
最近メディアでも話題となっている「サバの水煮缶」などもおすすめです。ただし、味噌煮やしょうゆ味付けのサバ缶は、塩分の過剰摂取につながるので避けてくださいね。
糖尿病患者が魚の刺身を食べる際に気をつけたいこと
前述した通り、糖尿病患者のタンパク質摂取には肉より魚が良いといわれています。
しかし、いくら身体にいいDHAやEPAが含まれているからといって、食べ過ぎによるカロリーオーバーや脂質の過剰摂取には注意しなければいけません。
糖尿病治療中の方がお魚の刺身を食べる際には、脂身の少ないマグロの赤身がおすすめです。マグロの刺身には、100gあたりタンパク質が21〜25gも含まれ、脂質は0.1〜0.2gしかありません。カロリーは120kcalほどで、ヘルシーな高たんぱく食材です。
塩分の摂り過ぎにならないよう、しょうゆは少な目を心がけ、味のアクセントとしてわさびなどの薬味を上手に取り入れるようにしましょう。
また、刺身がのったお寿司は酢飯が小さく握られているため、白米の食べ過ぎに注意してください。1貫あたりのカロリーは45kcal、炭水化物量は6.0g程度です。4貫食べると180kcal、炭水化物は24gにもなってしまいます。
最近のお寿司屋さんでは、シャリを少な目で注文することも可能なので工夫しながら楽しむようにしたいですね。
納豆が糖尿病にいい食材って本当?
 納豆が糖尿病リスクを低下させたり、血糖値を下げたりする効果があるといった情報を耳にしたことがある方も少なくないでしょう。実際のところ、納豆は糖尿病に良い食材なのか気になりますよね。
納豆が糖尿病リスクを低下させたり、血糖値を下げたりする効果があるといった情報を耳にしたことがある方も少なくないでしょう。実際のところ、納豆は糖尿病に良い食材なのか気になりますよね。
納豆の原料である大豆に含まれるタンパク質の一種「水溶性ペプチド」は、血液中にあるブドウ糖の吸収を促す作用があるといわれています。
膵臓から分泌されるインスリンは、細胞のレセプターと結合することで糖を体内に取り込みます。水溶性ペプチドは、このレセプターを活性化するだけでなく、レセプター自体の数を増加させる作用も期待されているのです。
これにより、ブドウ糖がスムーズに吸収されて血糖値が下がるといわれています。
ただし、糖尿病患者さんの膵臓からインスリンがほとんど分泌されていない場合には、血糖値を下げる効果はあまり期待できないので注意しましょう。
また、大豆タンパクに含まれる水溶性ペプチドは、グルカゴンと呼ばれるホルモンにも働きかけることがわかっています。
グルカゴンは、糖尿病患者さんに重篤な低血糖発作が起きた際に注射する薬剤としても知られていますが、もともと私たち人間の身体から分泌されるホルモンです。
血糖値が必要以上に下がり過ぎてしまったときには、このグルカゴンの働きによって正常な糖分濃度まで上昇させてくれます。
納豆の水溶性ペプチドは、血糖値を下げるだけではなく、低下しすぎないようにホルモン調整をする作用があるといえるでしょう。
さらに、納豆に含まれる「レシチン」という成分は、悪玉LDLコレステロールや中性脂肪を除去するパワーを秘めています。そのため、糖尿病患者さんに多くみられる動脈硬化や心筋梗塞などの「血管循環器系」の合併症予防にも効果的です。
納豆は、糖尿病患者さんのタンパク質補給源としてだけではなく、血糖コントロールのサポート・動脈硬化の予防をしてくれる食材なので、積極的に食生活へ取り入れると良いでしょう。
糖尿病の人が卵を毎日食べても大丈夫?
 糖尿病で食事療法をしている患者さんにとって、卵は大事なタンパク質の補給源です。
糖尿病で食事療法をしている患者さんにとって、卵は大事なタンパク質の補給源です。
医師から特別な指示がない限り、毎日食べても問題はありません。
それどころか、卵を食べることによってHDL-コレステロール(HDL-C)値が改善するといった報告もされているほどです。
これは、欧州糖尿病学会が2014年に発表したもので、糖尿病患者を2つのグループに分けて調査されました。1つ目のグループは週に卵を12個食べ、2つ目のグループは卵を週に2個未満しか食べないで3か月後の「脂質プロファイル」を比較しました。
すると、卵を多く摂取したグループの方がHDL-コレステロールの値が低下していたというのです。
一時期、「卵に含まれるコレステロールが身体に良くない」「卵は1日1個まで」と騒がれていたのを覚えている方も少なくないでしょう。しかし、2015年には日本の厚生労働省がコレステロールの摂取上限値を撤廃するなど、新しい動きがみられています。
卵1個(Mサイズ)には235mgのコレステロールが含まれていますが、1日に2~3個程度食べてもコレステロール値が上がることはありません。
卵黄には、リン脂質のひとつである「卵黄レシチン」と呼ばれる成分が含まれており、コレステロールの量を上手く調整しながら、善玉コレステロールを増加させる働きがあるといわれています。
また、卵を毎日食べると心血管系の疾患リスクが減少することもわかっており、糖尿病患者さんにとっても見逃せないでしょう。
卵をほとんど食べない人と比較すると、出血性脳卒中のリスクが26%減、虚血性心疾患のリスクが12%減という発表もされています。
糖尿病で高血糖が続くと、血管にも大きな負担をかけてしまうため、卵黄に含まれるレシチンなどの栄養成分をしっかり補っていくことが大切です。
ただし、脂質異常症と診断されている糖尿病患者さんの場合には、体内のコレステロールが増加しやすくなっているので、医師と相談のうえ「週に卵を何個までなら食べて良いのか」を確認しておく必要があります。
豆腐は糖尿病の食事療法に最適なタンパク質の供給源
 豆腐は、低カロリー・低糖質・高タンパクなので、糖尿病の食事療法では大変役立つ食材として注目されています。
豆腐は、低カロリー・低糖質・高タンパクなので、糖尿病の食事療法では大変役立つ食材として注目されています。
絹ごし豆腐なら、100gあたりのカロリーは56kcalしかありません。1丁を丸ごと食べたとしても、168kcalです。木綿豆腐は、100gあたり72kcalで、1丁216kcalといわれています。比較すると、木綿豆腐の方が高カロリーに感じますが、これは豆腐に含まれている水分量の違いが原因です。
糖質量は木綿豆腐の方が低く、100gあたり1.2gだけです。絹ごし豆腐は糖質1.7gなので、約0.5gの差があることになりますが、他の食品と比較すればかなり低糖質な食品といえるでしょう。
豆腐の原料である大豆は、昔から「畑の肉」と呼ばれているほどタンパク質が豊富で、ビタミンB、ビタミンE、カルシウムも豊富に含まれており、とても優れた食べ物です。
さらに、血糖コントロールには欠かせない「食物繊維」もたっぷり摂取できるため、食後の血糖値上昇を穏やかにする作用が期待できます。
また、豆腐の原料に含まれる「大豆イソフラボン」は、女性ホルモンに似た働きをすることで有名です。高コレステロールや高血圧を抑制し、動脈硬化の予防に効果的であることも豆腐の魅力のひとつです。
糖尿病ならプロテインの摂取に注意が必要
 筋肉づくりや、手軽なタンパク質補給のためにプロテインを飲んでいる人を良く見かけます。しかし、人工的に加工されたタンパク質は、「腎臓に大きなダメージを与えてしまう可能性も否定できない」と話す専門家も存在するのです。
筋肉づくりや、手軽なタンパク質補給のためにプロテインを飲んでいる人を良く見かけます。しかし、人工的に加工されたタンパク質は、「腎臓に大きなダメージを与えてしまう可能性も否定できない」と話す専門家も存在するのです。
特に、糖尿病を治療している方の多くは「糖尿病三大合併症」である、糖尿病神経障害、糖尿病網膜症、糖尿病腎症の発症を恐れているでしょう。
実は、プロテインの過剰摂取によって腎症を招く恐れがあるといいます。実際に、ある患者さんがパウダータイプのプロテインを多めに飲んでいたところ、腎機能をあらわす「尿アルブミン」の値が急激に悪化したとの報告もあがっています。
糖尿病で食事療法を行っていると、毎日の栄養バランスを考えるのが面倒に感じるときもあるかもしれません。しかし、今後の身体のことを考慮するならば、肉や魚、乳製品、大豆製品などの自然な食品からタンパク質を摂取することが重要となってきます。
糖尿病におすすめのプロテインは?
前述した通り、プロテインを日常的に摂取することは、腎臓への負担を考えると好ましくありません。
しかし、ある研究ではヨーグルトやチーズなどを作る際に発生するホエイプロテイン(乳清タンパク質)が、食後血糖値の急激な上昇を抑える効果があると発表されているのです。
ホエイプロテイン(乳清タンパク質)は、乳酸菌発酵液のことで、低脂肪・低カロリー、さらにタンパク質の合成を促進するアミノ酸が豊富に含まれているため、食事療法を行っている糖尿病患者さんには最適なプロテインといえるでしょう。
タンパク質の摂取目安量を守って糖尿病を治療しよう
糖尿病の食事療法では、患者さんに合わせたエネルギー量を指導されるのが一般的です。その中で、さまざまな栄養素をバランスよく組み合わせながら、1日の献立を考える必要があります。
指導されたエネルギー量のうち、55~60%を炭水化物から摂取し、タンパク質は体重1kgあたり1.0~1.2gを摂って、残りを脂質でまかなうといった計算方法です。体重50㎏の成人なら、1日のタンパク質摂取目安は約50gになります。
タンパク質が不足すると、ブドウ糖を代謝してくれる筋肉の量が減少してしまったり、下肢の機能が低下してしまったりする恐れが出てきます。そのため、乳製品、魚、大豆製品などを中心としたタンパク源から、しっかりと摂取することが大切です。
もちろん、タンパク質の過剰摂取は腎臓機能へ大きな負担をかけます。糖尿病腎症などの腎臓疾患を発症しないためにも、毎日適量を意識しながら継続して摂るように心がけてください。
まとめ
糖尿病を治療している患者さんの多くは、「できるだけ低糖質の食事をしよう」と、毎日努力しているはずです。
しかし、糖質を控えることばかりに気をとられてしまうと、タンパク質や脂質まで不足し、慢性的なエネルギー不足に陥っていることも少なくありません。極端なカロリー制限をしていると、低血糖を起こしやすくなり「糖新生」によって筋肉が分解され、筋肉量がどんどん減少していくのです。
糖尿病の治療では、食事療法とあわせて運動療法も大切な柱となるため、いつまでも「運動できる身体」を保つことも非常に重要です。
食事療法を実践していく際には、糖質制限とカロリー制限を混同しないように注意して、適切なタンパク質を摂取していくようにしましょう。
























