目次
糖尿病と便秘に関する基礎知識
弊社の商品開発チームの医師監修
Q. 糖尿病と便秘の関係とは?
A. 糖尿病による神経障害によって便秘に悩むことがあります。薬や生活習慣の改善が欠かせません
糖尿病で便秘はなぜ起きる?その原因やメカニズムについて
糖尿病においては、初期症状や合併症など様々な不調に悩まされることが多いです。その一つに挙げられる便秘。糖尿病患者の中で悩んでいる人も多いとされています。では、なぜ糖尿病から便秘になるのでしょうか?その原因やメカニズムについて、詳しく解説します。
糖尿病で便秘になる原因とメカニズム
糖尿病において恐ろしいとされている合併症には、いくつか種類があります。網膜症や腎症など、耳にしたことのある病気もあるでしょう。その中に、神経障害と呼ばれる合併症も含まれます。網膜症、腎症、神経障害は、糖尿病における三大合併症です。
神経障害によって足の異変やたちくらみを感じることがあり、胃腸の不調を抱えるようになる場合もあるため注意が必要です。胃腸の働きの低下によって、便秘や下痢、胸焼けなどを感じるようになります。内臓や器官の働きを司る自律神経に障害が起きることで便秘の症状が現れるため、糖尿病を発症したら気をつけたいです。糖尿病を発症してからおよそ3年後に神経障害は現れやすいため、自身の体調には敏感になっておくことが大切です。便秘を引き起こす神経障害は、糖尿病合併症の中でも発症するリスクが高いため、日頃から気をつけましょう。
糖尿病による便秘、具体的な症状一覧

糖尿病では、合併症の一つである神経障害によって便秘に悩むことがあります。便秘といっても人それぞれ現れる症状には違いがあるため、以下の状態を参考にしてみてください。
- 数日間、便がすっきりと出ていない
- トイレで頑張っても量が出ない
- 便秘が数日続いたかと思ったら、下痢になることもある
- お腹の張りを感じる
- 腹痛が現れる
一般的な便秘とよく似た症状がある中、便秘が続いた後に下痢に悩まされるという点が、糖尿病による神経障害ならではと言えるでしょう。今まで経験したことのある便秘とはちょっと違う、糖尿病になってから便秘に悩むようになったという異変を感じていたら、医師に相談してみるのも良いでしょう。糖尿病によって便秘が起きているかどうかを見極めることができます。
また、神経障害によって起きている便秘の場合は、胃腸においてその他の不調を感じることもあるため注意しておきましょう。食欲の低下や消化不良、吐き気や胸焼けも挙げられます。
糖尿病時の便秘や下痢は神経障害と関係がある?
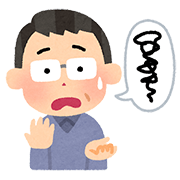
上記で説明したとおり、糖尿病時に起きる便秘や下痢は神経障害と深い関係があります。逆を言えば、糖尿病の合併症である神経障害が起きることで、便秘などの不調を感じるようになるのです。
この神経障害においては、他の網膜症や腎症に比べて早期発見が可能です。便秘になると自身で気づくことができますし、改善していきたいと思うはずです。そこで医師に相談するという流れによって、早期発見と改善が可能になります。
神経障害を起こすと、以下のような症状で悩まされることも増えます。症状によっては恐ろしいものもあり、日常生活が大きく左右されることもあるため注意しましょう。便秘や下痢以外にも、神経障害による症状はたくさんあります。
神経障害によって生じる症状一覧
- 手足の神経に異常が生じ、痺れや痛みなどの感覚異常が現れる
- EDになる
- 尿意を感じにくくなる
- いきなり心筋梗塞に襲われる
- 低血糖に気づかず、いきなり意識を失う
- 足の怪我に鈍くなり、傷が悪化しやすい
- 眠っているときによく足がつる
- 手足の先が火照りや冷えを感じる
神経障害において、最も恐ろしいのは痛みを感じなくなることです。足に傷ができているのに気づかず放置していたら化膿してしまった、切断を余儀なくされたという事例も実際に存在します。
また、尿意を感じにくくなったり、男性においてはEDに悩むことも増えます。手足の冷えや火照り、痺れや痛みまでも感じるようになったら、糖尿病の症状も進行していると考えて良いでしょう。
神経障害が思いもよらぬ事態を招くことを理解し、便秘や下痢などの症状を感じたら早めに診察を受けましょう。定期的に医師の診察を受けて、糖尿病が悪化していないか、その他の合併症が現れていないか確認することが大切です。
糖尿病から来る便秘は薬で改善できる?
糖尿病の神経障害によって起きる便秘は、早めに医師に相談することで治療や対策に進むことができます。今までは、糖尿病によって生じる便秘に対して、主に2種類の薬が利用されていました。

マグネシウム剤
身体に吸収されにくいという特徴を持つマグネシウムを摂取することで、浸透圧によって腸に水分を送りこむことができ、便が柔らかくなります。身体に優しい便秘薬と言えるでしょう。
刺激性下剤
腸の粘膜を刺激して排便を促すという薬です。便秘の症状がひどく、早くお腹をすっきりさせたいときに選ばれる薬となっています。
この2種類の便秘薬に加えて、平成27年にアミティーザという薬が新たに登場しました。腸管内にある受容体を刺激して水分を分泌していくことで、腸管の働きを活性化させるという目的を持った薬です。即効性がないため、一定期間使用する必要はあります。
また、最近になって新しく登場したリンゼスという便秘薬もあります。過敏性腸症候群にのみ効果が期待できるとされている薬であり、仕組みはアミティーザと大きく変わりません。一点変わることといえば、大腸の過敏によって感じる痛みを軽減してくれる働きがあります。過敏性腸症候群と診断されて、痛みにも悩まされている人には適している薬です。
糖尿病による便秘の治療法について
糖尿病によって生じる便秘や様々なお腹の不調を改善してくれる薬が誕生している中で、病院の医師に相談した際にはどのような治療法を提案してもらえるのでしょうか?上記で紹介した便秘薬を処方されることもある中、その他に治療法は存在するのか、調べてみましょう。
最も重要となるのが血糖値のコントロール
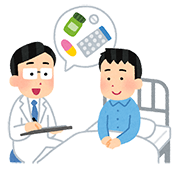
糖尿病による便秘は、神経障害が起きていることで現れる症状です。そこで、重要となるのが、糖尿病を根本から改善していくことです。血糖値が正常に保てなくなる糖尿病において、しっかりコントロールしていこうという治療が一般的です。
具体的には、アルドース還元酵素阻害薬という薬を用いて治療を進めることが多いです。アルドース還元酵素阻害薬は、ソルビトールという物質が細胞内に蓄積されるのを予防する働きがあります。ソルビトールはブドウ糖が変化したものであり、神経細胞の中に入り込むことで様々な神経障害を引き起こします。服用を続けることで血糖値に効果が期待できるアルドース還元酵素阻害薬ですが、一部副作用や注意点もあるので理解しておきましょう。尿の色が赤や黄褐色になることがあり、稀に肝臓の障害が起きることもあるため経過観察が必要です。医師から副作用の説明もあるはずなので、しっかりと聞いて理解しておくことが大切です。
整腸薬を飲んで便秘の改善を図る
市販薬や病院から処方される便秘薬の種類は増え、糖尿病によって起きている便秘も以前よりはスムーズに改善できるようになりました。下剤やいわゆる便秘薬と呼ばれる薬は、溜まっている便をしっかり出していくことが目的です。一方、整腸薬は腸内環境を整えながら自然に排便できるよう促してくれるものです。
腸内の善玉菌を増やすのが大きな役割であり、悪玉菌の増殖を抑える働きもあります。整腸薬と呼ばれる種類の薬は、薬局でも気軽に購入できます。また、病院でも処方されることがあり、強い副作用などを心配せずに利用できるという安心感があるでしょう。
日常生活で実践できる便秘対策とは
糖尿病からは、様々な合併症によるリスクが想定されます。病院で診察を受けながら治療方針を決めていくと同時に、日常生活において自身ができる対策を取ることも必須となります。特に便秘に関しては、毎日の気分を左右する存在であり、外出などの予定があるときにも支障をきたす恐れがあるため、早めに改善していきたいです。治療を続けながら以下の対策を取って、少しでも早く便秘から開放されましょう。
便秘を防ぐ食事を心がけよう
日常生活で便秘の改善を図っていく際には、食事の見直しが欠かせません。食事において注意すべきポイントはたくさんあり、できることから始めると続けやすいです。以下のポイントを押さえて、楽しく食事をしましょう。
1 食事の時間を決めて規則正しい生活を
毎日決まった時間に一日3食食べていると、お通じのリズムも整ってきます。朝昼晩、規則正しく食事をすることで生活リズムが整うため、健康にも良いです。規則正しい生活は糖尿病を改善していく上で重要となります。食事の時間を決めておくことから始めてみましょう。さらには、毎日決まった時間にトイレに座る時間も作ると、便秘の改善が期待できます。

2 食物繊維をたっぷり摂取しよう
すっきりと適量を排便するためには、食事内容も重要です。バランスの取れた食事が何よりも大事ですが、その中でも繊維質を豊富に含む食物繊維を積極的に摂取してみましょう。便のかさを増やし柔らかくしてくれたり、腸の蠕動運動(ぜんどううんどう)を活発にする働きがあります。水溶性食物繊維と不溶性食物繊維をバランスよく摂取することで便秘の症状が徐々に改善されていくため、食材選びにも注意しながら食事を作りましょう。それぞれの食物繊維にどのような食材が含まれるのか、一部を以下に紹介します。
- 水溶性食物繊維・・・海藻類、いも類、大麦、ライ麦、こんにゃくなど
- 不溶性食物繊維・・・大豆、ごぼう、きのこ、ココアなど
食物繊維の一日の摂取量は20~25gが目安になっており、現代人はこれよりも少ないのが現状です。食物繊維は緑黄色野菜や豆類、海藻類、きのこ類、いも類など様々な食材に含まれます。根菜類にも豊富に含まれるため、煮物や炒め物、具沢山味噌汁などで積極的に摂取しましょう。食物繊維の種類に注目しながら、それぞれをバランスよく摂取して便秘を改善していけると良いですね。
3 こまめな水分補給も大事

食物繊維をバランスよく摂取するのを心がけながら、こまめな水分補給も行ないましょう。便秘の原因の一つには、水分不足が挙げられます。さらに、糖尿病で高血糖の状態が続くと、喉の渇きを感じるようにもなります。
便秘改善にも有効なこまめな水分補給においては、どんな飲み物を選ぶかも重要です。1日1.5リットル以上が水分摂取量の目安になっており、朝起き抜けに水を一杯飲むだけでも腸の蠕動運動を促すことができます。食事においてスープや味噌汁などを飲むようにすると、さらに水分をしっかり摂取できるでしょう。また、以下の点に注意しながら、水分補給を心がけましょう。
~正しい水分補給のポイント~
冷たい飲み物は控えて、常温で飲むようにする
お茶や水がおすすめ
清涼飲料水や炭酸飲料には多くの糖分が含まれているため、糖尿病のときには返って逆効果になる
適度な運動を日課にしてみよう
食事内容や水分の摂取量に注目することが便秘改善においては重要と言えますが、それと同時に適度な運動を日課にすることで、さらに効率よく便秘を解消していくことができるでしょう。
適度な運動は、腸の蠕動運動を活性化させてくれます。また、汗ばむ程度の運動を行なうと、自然と水分摂取量を増やすことができるでしょう。運動不足が糖尿病を招くとも言われているほどなので、適度な運動を続けていると糖尿病改善にもつながります。
運動が苦手な人にとっても続けやすい、ウォーキングやジョギング、縄跳び、水中ウォーキングなどで十分効果は期待できるため、時間を見つけて身体を動かしてみましょう。
まとめ
糖尿病は、様々な合併症を引き起こす恐ろしい病気です。一見いつもの不調かと思われがちな便秘も、神経障害によって起きている可能性があります。そこで、血糖値のコントロールを行ないながら、日常生活で実践できる対策も始めていきましょう。定期的に医師の診察を受けながら、食事内容の見直しや運動を心がけることで便秘の症状も徐々に改善されていきます。
また、神経障害は便秘以外の怖い症状を引き起こす恐れもあるため、知識を得ながら日常生活で対策を始めましょう。糖尿病は、早期発見ができると改善していける病気です。上手に付き合うことで無理なく過ごせるため、日々自身の体調には敏感になっておきましょう。便秘が改善されると気分もすっきりし、毎日を快適に過ごせるようになります。
























