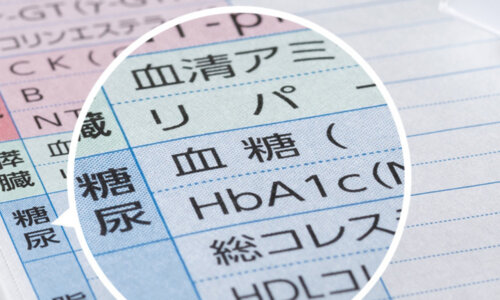目次
糖尿病の初期症状は爪に現れるって本当?
糖尿病は血液や神経の働きを悪化させます。ところが、即座にひどい症状が出ることが少ないため、検査するまで発見できない場合が多いのです。
中でも、見落としがちな糖尿病の初期症状として「爪の異変」が挙げられます。
Q. なぜ糖尿病患者は爪に症状が出やすいのですか?
A. 糖尿病とは、血管がどんどん老化する病気です。血糖値が高いと血管が傷つき、動脈硬化が進みます。血管が細くなり、 ボロボロになり、 血流が悪くなります。
すると、血管を通して運ばれる「酸素」と「栄養」が届きにくくなり「老廃物」の回収が悪くなります。身体の末端にある爪にまず症状が出ます。
また、栄養が行き届かないので免疫力も低下しているため、さまざまな菌(水虫菌)に感染しやすくなっています。
弊社の商品開発チームの医師監修
糖尿病になると爪に異変が起きる理由
糖尿病の代表的な症状といえば、インスリンの分泌や働きが低下し、血糖値が上昇してしまうことです。高血糖になると血管が傷つき、細くボロボロになります。糖尿病の人の血管の老化スピードは、実に健常者の2倍以上ともいわれているのです。
その結果、全身に栄養が行き届かなくなることで、様々なトラブルが起こります。そのひとつが、「爪の異変」です。とくに爪のような身体の末端にある部位はその影響を受けやすく、爪に栄養が届かなくなるため状態が悪化してしまうのです。
手の爪より足の爪に注意
糖尿病による爪の異変は、一般的に手の爪よりも、足の爪に現れることが多いです。糖尿病を発症すると、とくに足の末端にある血管が細くなりやすく、それによって傷の治癒力が低下し、足の爪に症状が出やすくなります。
ですので、糖尿病を疑う際は、手よりも足の爪をチェックするとよいでしょう。
糖尿病予備軍と診断されたことがある方や、普段から高カロリーで味の濃い食事をよく摂っている方で、「足の爪が黄色く変色している」「爪が厚くボロボロになっている」「巻き爪」などの症状が見られる場合、糖尿病の初期症状の疑いがあります。
爪以外にも知っておきたい糖尿病の初期症状

糖尿病は自覚症状が少なく、発見がどうしても遅くなりがちです。爪の異常も、なかなかそれだけで糖尿病とは気付けないところが恐いですよね。爪のトラブル以外にも、次の症状がみられたら注意が必要です。
- のどの渇き
- 頻尿
- 空腹感
- 疲労感
- 目のかすみ
- 皮膚の乾燥やかゆみ
- 手足の感覚が低下やピリピリした痛み
- 性機能の低下(ED)
- 傷や出血が治りにくい
これらは糖尿病の代表的な初期症状です。多くが神経や血液の問題から発症し、全身にさまざまな軽微な症状として現れます。
そして糖尿病を発症すると、もれなく血糖値が上昇します。いきなり病院で検査するのは不安という場合や、検査に行く時間が取れない場合は、まずは血糖値を測定してみましょう。
日本の薬局では血糖値測定器はほとんど手に入りませんが、糖尿病お助け隊では、医師からも推奨されている『ACON血糖値測定器』を扱っています。
医師も認めた血糖値測定器として
歯科医・内科医の連携プロジェクトにも協賛中です
アメリカからの発送となるため、1週間ほどでお手元に届きます。糖尿病が心配な場合は、痛みなく自宅で簡単に血糖値を測定できますので、まずは異常がないか調べてみるとよいでしょう。
爪に現れる糖尿病の初期症状
糖尿病になったら、実際、爪にどのような変化が起きるのでしょうか?糖尿病の初期症状として現れる爪のトラブルには、次のような症状があります。
爪肥厚(爪が異常に厚くなること)

爪肥厚(そうひこう)とは「爪が分厚くなった状態」のことです。爪が厚くなると、爪が割れやすくなったり、場合によっては爪が剥がれることもあります。爪が割れたり剥がれたりすると、そこから雑菌が入って化膿し、さらに悪化する可能性があります。とくに糖尿病の場合、免疫力が低下するため、白癬菌に感染しやすいので注意が必要です。
糖尿病の初期症状の他にも、爪肥厚は長時間にわたって爪が圧迫されたり、水虫の一種である白癬菌に感染した場合にも起こります。
巻き爪

巻き爪とは文字通り爪が巻いた状態になってしまうこと。爪の端が内側に曲がってしまい、指の肉に食い込んでしまいます。
爪にはもともと巻いてしまう性質がありますが、これがより顕著に現れるのが巻き爪の症状です。巻き爪がひどくなると指先に傷がついてしまい、化膿や炎症を起こしてしまいます。
糖尿病による巻き爪もまた、爪に栄養が行き渡らずに正常に伸びなくなってしまうことが原因です。糖尿病の他に、深爪や靴のサイズが合わないと巻き爪になります。
爪に白い線が入る

糖尿病の初期症状には、爪が白く濁ったり、爪に白い線が入ってしまうという状態もあります。
これもまた、糖尿病によって爪にまで栄養が回らずに成長が均一でなくなり、濁りや白線が出てしまうのです。
爪の変形

その他に、爪に段差ができるなどの爪の変形も、糖尿病によって起こる爪のトラブルのひとつ。
爪の変形は、深爪、直立時や歩行時の足の向き、靴のサイズが合っていない場合などにも起こります。爪がぼこぼこしていたら、姿勢や靴のサイズにも気を付けましょう。
爪水虫(爪白癬)

爪のトラブルの悪化などにより、真菌に感染して起こるのが「爪水虫」です。足の水虫と同じ白癬菌が原因であることから「爪白癬」とも呼ばれます。爪水虫は、爪のトラブルを放置していた場合や、糖尿病による血行不良や免疫力の低下によって起こります。
糖尿病になると、血流が悪くなることで皮膚自体が弱まり、感染症のリスクが高まります。そのため、日頃からフットケアとして水虫がないか、確認することが大切です。
糖尿病で爪に異変が起きたときの対処法

爪の異常を発見したら、まずは医師の診断を受けましょう。爪の異変の原因が糖尿病なのか、それとも別の問題なのか、素人目には判断できません。もし仮にそれが糖尿病の初期症状だった場合、早期発見ができれば、症状の進行を抑えることも可能となります。
糖尿病の検査は基本的に採血だけでできますから、気負わずにかかりつけのお医者さんに相談してみましょう。
爪水虫の治し方
糖尿病の爪のトラブルの中でも、とくに注意したいのが「爪水虫」です。前述した通り、糖尿病の人は水虫になりやすく、悪化しやすい傾向があります。
また、糖尿病とは気付かずに悪化して症状が出ていた場合、足の神経が弱り感覚がなくなっているケースも考えられます。そうなると細菌に感染しやすくなり、最悪の場合、足が壊疽し切断という可能性すら出てくるのです。
爪水虫には白癬菌を殺す内服薬・ラミシールも有効ですが、何より日々の管理が重要です。
そこでおすすめしたいのが、『ファンガソープ』です。

ファンガソープは、皮膚科医からも推奨されている皮膚トラブル対策に有効な天然ソープです。主成分には、白癬菌をはじめとする真菌を99.9%殺菌する効果のあるティーツリーオイルを配合しています。
なぜ、爪水虫対策にソープが重要なのか?
その理由は、市販のボディソープは水虫や爪水虫を悪化させる可能性があるからです。
市販のボディソープでは、真菌などの悪い菌は殺菌できません。それどころか、雑菌から皮膚を守る良い菌を洗い流してしまい、逆に皮膚トラブルを悪化させてしまうのです。
対して、ファンガソープの主成分であるティーツリーオイルは、体に良い菌は残し、悪い菌だけを殺菌する働きが認められています。日頃からファンガソープで洗うことで、白癬菌などの雑菌の増殖・感染を防ぎ、爪水虫の予防が行えます。
すでに爪水虫の症状が見られる場合は、こちらのセットがおすすめです。

まずはファンガソープEXで白癬菌を洗い流し、殺菌します。その後、ファンガクリームを足全体に塗り、爪の上からもすり込むように塗りましょう。ティーツリーオイルを高配合したファンガクリームで蓋をすることで、白癬菌を密閉して殺し、徹底的に増殖を抑えます。
その後は、爪水虫専用の「チモールリキッド」を爪と皮膚の間に注入するように塗布しましょう。チモールリキッドには、水虫菌に即効性のある「チモール」をはじめとした3大成分を配合しています。
毎日入浴時にこの3ステップを続けることで、糖尿病の人がなりやすい水虫と爪水虫を同時に対策できます。
日常的に行いたい糖尿病のフットケア
爪水虫以外にも、爪のトラブルの予防・改善には日頃のケアが必要です。爪のトラブルを放置していると、爪が割れたり、指に爪が食い込んで出血したり、雑菌に感染したりなどの様々なトラブルに発展します。
爪に異変が見られる場合や糖尿病の人は、日頃から以下のフットケアを行いましょう。
1.爪の状態をチェック
糖尿病による爪のトラブルを悪化させないためには、日頃から足の爪の状態をチェックすることが大切です。
普段、爪切りをする際は、
- いつもよりも爪が厚くなっていないか
- 巻き爪になっていないか
- 指に爪が食い込んでいないか
- 爪が白濁していないか
- 爪にヒビや筋が入っていないか
- 変形していないか
をしっかりと見ておきましょう。
軽度のうちに爪のトラブルを発見できれば、セルフケアだけで症状が完治することもあります。
2.正しく爪を切る

糖尿病の人は、爪の切り方にも注意が必要です。深爪などをして指先や爪を傷つけてしまうと、そこから細菌が入り、ひどくなると下肢切断という最悪の状況にまで悪化しかねません。
正しい爪の切り方は、『爪先が真っ直ぐになるよう四角く切る』ことです。爪の両角のとがった部分は、やすりなどを使って整えましょう。
よく爪を切る際に、爪を丸く整える人がいますが、これはNG。爪を丸く切ると、巻き爪が起こりやすくなります。
すでに爪が厚くなっている場合や、巻き爪が起こっている場合など、爪が切りにくい時は「爪切りバサミ」を使うと良いです。ハサミタイプであれば、爪切りを無理やり爪に食い込ませる必要はなく、楽に爪を整えることが可能です。
3.足を清潔に保つ
爪水虫をはじめ、足の潰瘍、さらには壊疽(えそ)の原因となるのが、外部からの細菌の侵入です。とくに爪の異常により小さな傷や爪の割れが起きている場合、気付かないうちに菌が侵入するリスクが高いです。
爪に異常が見られた場合は、足を常に清潔に保つことを心がけましょう。細菌の侵入を徹底的に防ぐには、先ほどご紹介した「ファンガソープ」がおすすめです。
柔らかいスポンジやタオルにファンガソープを含ませてよく泡立てたら、足の指の間や爪までしっかりと洗いましょう。

保湿クリームなどでのケアも有効ですが、水分は水虫菌のエサになるので、過度な保湿には注意が必要です。
また、爪や足に傷やひび割れがある場合は、ケアの仕方を主治医に相談してみましょう。
足の清潔さをキープするためには、靴下の着用も有効です。素足のままでは細菌に触れやすくなってしまいますが、清潔ではき心地のよい靴下を履けば細菌の感染を防ぎやすくなります。
4.余裕を持った靴を使用する
靴のサイズも爪や足のケアにとっては重要です。サイズ違いの靴を使用し続けると、足の血管や神経を圧迫してしまったり、指や爪が押しつぶされて傷ついたり爪が変形、あるいは割れてしまったりします。
爪の異常を感じたのであれば、靴の形状やサイズを見直して、自分の足にフィットした靴を履くようにしてください。専門のシューフィッターやシューズショップの専門スタッフに相談して、自分の足にぴったりの靴を見つけるとよいでしょう。
【警告】爪水虫を治せば良い!という訳ではない
糖尿病になると爪のトラブルが起きやすいので、前述した通り、フットケアや爪の治療を行うことは大切です。しかし、爪のトラブルが治ったからと言って、それで終わりではありません。
もし、すでに糖尿病を発症している場合、あなたの血管は日々ボロボロになっています。爪のトラブルを治したところで根本的な問題は解決していないのです。
糖尿病を進行・悪化させる原因は、「血管の老化・血流の悪化」にあります。
糖尿病の方は、1にも2にも
- ・血管を丈夫に
- ・血管の老化を防ぐ
- ・血流を良くする
- ・血管内の血栓やプラークを取り除く
これら血管のケアを徹底的に行うことが重要です。
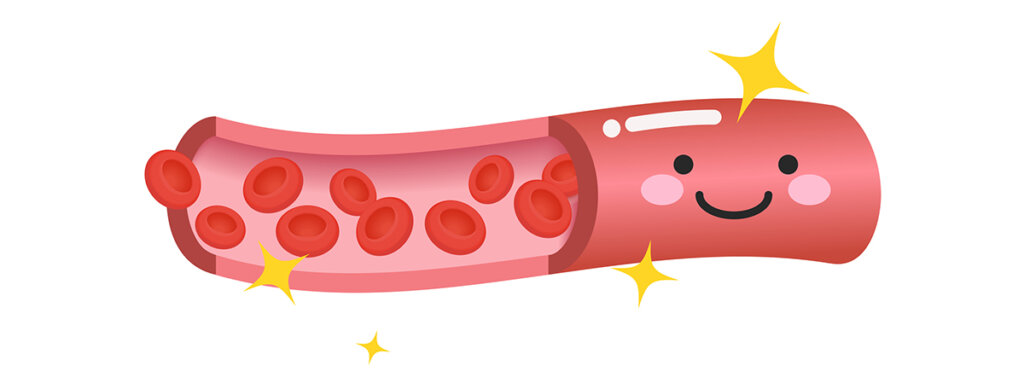
また、感染症になりやすいので、爪水虫などの菌はできるだけ早く撃退し、菌に侵されない体づくりをしましょう。
糖尿病お助け隊では、「血糖値測定器」や「爪水虫対策セット」の他にも
「副作用なしで血糖値を下げるサプリメント」や「血管を若返らせるドリンク」など、様々な商品を取り揃えています。
全て臨床試験に基づき、しっかりと効果が期待できる商品です。
もし効果に少しでも不満があれば、
遠慮なくご返品いただける制度も整えております→ 90日間全額返金保証
糖尿病対策は、早期ケアがカギです。
ぜひこちらの店舗も合わせてご覧になってみてください。