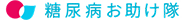目次
糖尿病とむくみに関する基礎知識
弊社の商品開発チームの医師監修
Q. よく足がむくむのは糖尿病のサイン?
A. 足のむくみは一時的なものが多いが、なかなか治らない場合は糖尿病の症状かも。むくみの原因から対処法まで解説します。

足のむくみの原因は糖尿病?
足のむくみの原因は、大きく2種類あります。
まずひとつは、一時的な原因によるむくみです。デスクワークなど長時間同じ姿勢を続けたことで血液の流れが悪くなったり、水分が溜まったりすることでむくみが起ります。また、年齢を重ねるごとに体のポンプ機能を果たす筋肉量が低下し、血液の循環が悪くなるので、高齢者はとくにむくみが出やすくなります。このような一般的なむくみの場合、一晩寝ると治るものがほとんどです。
一方、靴が履けないくらいパンパンに足がむくんだり、左右の足の太さが明らかに違う場合など、一晩で治らない重度のむくみは何らかの病気が原因だと考えられます。
病気が原因で起きるむくみは、症状が日ごとに増していき、靴が履けないほど足が太くなったり、数日で体重が数キロ増えたりする特徴があります。
足のむくみに加えて次の症状がみられる場合は、「糖尿病」の可能性が考えられます。
- 血糖値が高い
- ひどくのどが渇く
- トイレの回数が増える(頻尿)
- 尿が泡立っている
- 食べても体重が減る、理由もなく痩せる
- 体が疲れやすい
- 太る
- 視力が落ちた
- 手や足にタコやイボがよくできる
糖尿病には特有の自覚症状がなく、気付かずに進行しているケースが実に多いので注意が必要です。むくみ以外にも上記の症状が出ている場合、糖尿病の疑いがあります。
糖尿病かどうか、判断する目安のひとつとしては「空腹時血糖値」があります。空腹時の血糖値が126㎎/dL以上の場合は「糖尿病」、110~125㎎/dLの場合は「糖尿病予備軍」が疑われます。
最近は自宅でも簡単に血糖値の測定ができますので、不安な方はまずは血糖値を測定してみましょう。
こんな症状に注意!糖尿病が手足に引き起こす症状
手足がむくむ
糖尿病による手足のむくみは、糖尿病が原因として発症する3大合併症のひとつ「糖尿病性腎症」の代表的な症状です。糖尿病によって腎機能が低下した結果、体内の不要な水分や老廃物が排出できなくなり、むくみを引き起こします。
糖尿病性腎症によるむくみは初期段階では現れず、かなり進行した状態になって症状が現れます。つまり、現在、悩んでいるむくみが糖尿病によるものだった場合、すでに病気が進行している可能性が高いのです。
糖尿病性腎症は病気の進行段階によって第1期~第5期まで分かれており、むくみの症状が現れるのは第3期です。第3期に至るまでは10〜20年と長く、特有の症状がありません。しかし、3期以降の進行はきわめて速く、むくみの症状が出てから2〜5年の間に進行し、5期に至ると透析治療が必要となります。
このように「糖尿病性腎症」はむくみ以外に自覚症状が少ないこと、また、進行スピードが急速であることから、糖尿病性腎症が原因で透析治療を開始する患者さんがとても多いです。
一晩寝て治るようなむくみなら心配する必要はありませんが、すでに糖尿病と診断されている場合、糖尿病性腎症の可能性もありますので、きちんと医師に相談し、迅速に適切な治療を行う必要があります。
手足がしびれる
むくみ以外にも、糖尿病に多く見られる初期症状に「手足のしびれ」があります。手足のしびれは、糖尿病の3大合併症のひとつである「糖尿病性神経障害」によって起こります。これは糖尿病患者の中で最も発症する人が多く、早期から起こりやすい合併症状のひとつです。
糖尿病性神経障害によるしびれは、両手両足の左右対称部分に現れるという特徴があります。病気の初期段階では足の指や足の裏にしびれやピリピリとした痛みを感じ、進行すると手の指にも症状が現れるようになります。
ただのしびれだからと放っておくと、病気の進行が進んでしまうだけでなく、強い痛みを伴う場合もあり非常に危険です。さらに神経障害が進むと、逆に感覚が鈍くなって痛みを感じにくくなります。そうなると足の傷などにも気付きにくくなり、知らないうちに足潰瘍(あしかいよう)や壊疽(えそ)といった足の切断を招く深刻な病状にまで発展するリスクがあります。
薬の副作用で手足がむくむことも
上記のほかには、糖尿病治療薬の副作用でむくみが生じるケースもあります。内服薬では「スルホニル尿素薬」や「チアゾリジン薬」などを服用している場合、ほかの薬との併用などにより身体がむくむ場合があります。また、極端な高血糖に対してインスリン注射をした場合は、「インスリン浮腫」と呼ばれるむくみが出ることもあります。
これらのインスリン抵抗性の改善によって生じるむくみの症状は、男性よりも女性の方が多い傾向にあります。
手足のむくみはなぜ起きる?
手足がむくむ原因は、体内の水分のバランスが崩れてしまうためです。
人間の体のおよそ60%は水分で成り立っており、その3分の2は細胞内にとどまっています。残りの3分の1の水分は、細胞と血管の間で酸素や栄養などを受け渡す役割を担っています。通常は、体内の水分バランスは一定に保たれていますが、何らかの理由でバランスが崩れると、一度細胞へと移った水分が血管内に戻りにくくなり、細胞間を埋めている水分が異常に多くなってしまうことがあります。この状態がむくみです。
体内の水分バランスが崩れてしまう要因はさまざまです。
デスクワークや飛行機での長時間の移動などで同じ姿勢をとりつづけると、血液の循環が悪くなり、水分バランスが乱れてむくみが発生します。立ち仕事もまた、重力の影響を受けて足に血液が滞り、むくみを起こします。
この他にも、アルコールの摂取、水分や塩分の摂り過ぎ、ストレスなどもむくみの原因です。女性の場合は、ホルモンバランスが変化する生理前や妊娠中、更年期といった時期は自律神経の乱れにより血行が悪くなるため、むくみを感じる人も多いでしょう。
このほか、薬の副作用や病気が原因で起こる場合もあります。
糖尿病とむくみの関係性
糖尿病が原因のむくみの場合、腎臓の機能が正常に働いていないために起こります。
血糖値が高い状態が続くと血管が狭くなったり詰まりやすくなったりして、血液の流れを止めてしまうことがあります。この状態を「動脈硬化」といいます。動脈硬化により血液が十分に流れないと、全身への適切な栄養や酸素の供給が上手く行われないため、臓器に障害が起こってしまいます。
腎臓内には毛細血管が毛糸玉のように集まった糸球体と呼ばれるものが約100万個存在します。心臓から送られてきた血液が糸球体のなかでろ過され、老廃物や塩分などの不要な物質を尿として体外に排出します。そうして私たちは体内の血液をきれいに保っています。
しかし、糖尿病の影響で糸球体の中の毛細血管内で動脈硬化が起きると、ろ過機能が正常に働かなくなってしまいます。その結果、体内に不要物や水分が溜まってしまい、むくみとなって体に現れるのです。
糖尿病で怖いのは合併症を引き起こすこと
糖尿病患者の多くは、飲酒、喫煙、運動不足、ストレスなどの生活習慣が原因であるケースがほとんどです。糖尿病自体には痛みなどの自覚症状はなく、医師の指示に従ってきちんと治療を行えば、日常生活に支障もありません。
しかし、糖尿病の本当の怖さは「合併症」にあります。
糖尿病の治療が十分でなかったり、気付かないうちに病気が進行していたりすると、体のさまざまな部分に悪影響が起きて、合併症を引き起こします。糖尿病の合併症は失明や腎不全を引き起こしたり、心臓病や脳卒中などの死のリスクが高い病気に直結したりと、深刻なものが多いため、気を付けなければなりません。
このような合併症を発症しないためにも、まずは飲酒や喫煙などの体に悪い生活習慣を改善すること。さらに、糖尿病治療の基本である「食事療法」や「運動療法」をきちんと行いながら、血糖値を上手くコントロールをしていくことが大切です。
糖尿病による合併症の種類
糖尿病にはさまざまな合併症があります。中でも代表的なものが、先ほどお伝えした「糖尿病性腎症」「糖尿病性神経障害」、そして「糖尿病性網膜症」です。これらを糖尿病3大合併症と呼びます。
糖尿病3大合併症は主に細かい血管が集まっているところに障害が起きることから「細小血管障害」とも呼ばれます。対して、大きな血管に障害が起こることを「大血管障害」と呼び、動脈硬化などがこれにあたります。
糖尿病性網膜症
糖尿病性網膜症は、成人後の失明原因第1位の病気です。毎年3000人以上が糖尿病を原因として失明しているというデータもあります。
血糖値が高い状態が続くことで網膜にある細かい血管が詰まったりもろくなったりして、血液が十分に流れず障害が起こります。自覚症状がほとんどなく、知らず知らずのうちに失明寸前まで進行していたというケースもあります。早期発見・早期治療のためには、内科だけでなく眼科でも定期的に検診することが大切です。
糖尿病性腎症
前述した通り、糖尿病性腎症は、腎臓内の血管に障害が起こって腎臓の機能が悪くなる病気です。代表的な自覚症状としてむくみが挙げられますが、むくみが現れた時点では病気はかなり進行している状態です。さらに病気が悪化すると、自力で血液を浄化できないため、透析療法が必要となります。
糖尿病性腎症の進行を防ぐためには、タンパク質の過剰な摂取と激しい運動は控えなければなりません。
糖尿病性神経障害
糖尿病性神経障害は、全身をめぐる神経に障害が及ぶことで、さまざまな症状を引き起こします。特に多いのが手足のしびれや痛みです。きちんと治療を行えば症状は緩和されますが、治療を怠ると強い痛みがあらわれたり、逆に感覚が鈍くなってしまい気付かないうちに怪我をする危険などがあります。
神経障害が起こる原因としては、糖尿病によって「ソルビトール」と呼ばれる障害を起こす物質が神経細胞に蓄積することや、動脈硬化の影響で血流が悪化し酸素や栄養が不足することなどが考えられますが、はっきりとした原因はまだわかっていません。
糖尿病性神経障害は、しびれ以外にも下痢や吐き気、胃もたれなどその症状は全身に及びますが、きちんと治療を続けることで多くの場合、症状は緩和されます。
動脈硬化(脳卒中・心臓病)
糖尿病によって血糖値が高い状態が続くと、血管に大きなダメージを与えます。細い血管が集まる目や腎臓で合併症が起きるように、太い血管でも怖い合併症を引き起こします。それが「動脈硬化」です。
動脈硬化になると、血管の内側にさまざまな物質が蓄積した結果、血管が厚く硬くなるだけでなく、プラークと呼ばれる隆起を作ってしまいます。このプラークが剥がれて血管に詰まってしまうと、脳卒中や心筋梗塞を引き起こすのです。
動脈硬化は糖尿病だけでなく、高血圧や喫煙なども原因のひとつとされています。
手足のむくみがひどい時の対処法
むくみが一時的な症状である場合は、マッサージやストレッチなどで体をほぐし、血流を促してあげると良いでしょう。冬場の寒い時期や室内の空調による冷えもまた血流を悪化させ、むくみの原因となるので、入浴などで体を温めるのもおすすめです。
また、むくみの解消には、利尿作用のある食べ物も効果的です。具体的には、「きゅうり、すいか、りんご、バナナ、昆布、小豆、豆腐、豚肉、かぼちゃ」などがあります。
一方、糖尿病が原因でむくんでいる場合は、血液中の糖分をコントロールすることが何より重要です。
自宅で血糖値コントロールを行う際には、「ヘモグロビンA1c下がらなかったら全額返金セット」がおすすめです。
このセットには、「糖尿病対策に有効な2種のサプリメント」と「ACON血糖値測定器(※定期初回のみ)」が含まれています。
これらを使い、血糖値を徹底してコントロールするための4つの対策が行えます。
| 1.インスリンの分泌や働きを向上させる
米国糖尿病学会が推奨する14成分を配合した「グルコサポート」、臨床試験で実証された特許成分配合の「マイタケオール」、2つのサプリメントがインスリンの分泌と働きを強力に改善します。
2.食後の血糖値を測定する 3.食後血糖値を見ながら、食事の糖質量を調整する 4.食後30分、60分、120分の血糖値が目標より高ければ、即下げるアクションを取る |
この4つの対策を心がければ、血糖値のコントロールは万全です。根本的なインスリンの働きを回復させつつ、血液中の糖分を徹底的にコントロールすることで、糖尿病の指標となるヘモグロビンA1c(血糖値の平均値)は下がります。
その結果、糖尿病の進行を防ぐことにつながり、むくみなどの症状の改善にも期待ができるでしょう。
ヘモグロビンA1cが下がらなかったら
全額返金します。まずはお気軽にお試し下さい。
上記の他に、病院では血糖値の状態によって、食事・運動療法に加えて内服薬やインスリン注射などの薬物治療を行います。
これらの治療を行ってもむくみの改善が見られない場合は、糖尿病によって途絶えてしまった血流を再び開かせる「血行再建術」という手術を行う選択肢もあります。
痛みを伴うときの対処法
むくみがひどくて痛い、歩けないという状態が繰り返し起こる場合、「間歇性跛行(かんけつせいはこう)」という症状に陥っている可能性もあります。
間歇性跛行は血管の病気である動脈硬化が原因で発症するものなので、マッサージや湿布を貼っても治りません。痛みが出ても休むと治まることがあり、一時的なものと思われがちですが、動脈硬化は足だけでなく脳や心臓の血管にも及んでいることがあります。つまり、そのまま放置してしまうと脳卒中や心筋梗塞を引き起こす可能性があるのです。
このような重大な病状を防ぐためにも、間歇性跛行が見られる場合はすぐに病院を受診しましょう。
糖尿病患者に向けた専用の靴下がある
高血糖の状態が長く続き、糖尿病が進行すると足に異常が出やすくなります。
体の抵抗力が弱まることで細菌に感染しやすくなったり、動脈硬化によって足のキズが治りにくくなったりするためです。さらに、糖尿病性網膜症も併発していた場合、視力が低下しているので足の異常に気付かないまま深刻な状態に陥ることも。
そうならないために、糖尿病患者が行いたいのが「フットケア」です。
フットケアでは、大切な足を守るために清潔に保ったり、足を観察してケガがないかこまめに確認したりすることで病気の悪化を防ぎます。このフットケアの一環として、糖尿病患者に向けた専用の靴下もあります。
むくみがヒドイ時は、吸湿性の良い綿素材のもの、特に5本指靴下がおすすめです。靴下の重ね履きやサイズがきつめのものを履くと、逆に血行を悪くしてしまうので注意しましょう。
糖尿病の治療方法とは?
糖尿病を一度発症すると、現代の医療では完治は難しく、長い時間をかけて病気と付き合っていかなければいけません。その方法としては、高い血糖値を下げるために血糖を上手くコントロールすることが挙げられます。
血糖をコントロールする治療としては、以下の3つがあります。
食事療法
朝食、昼食、夕食の3食を規則正しくバランスよく食べること。食べてはいけない食べ物はありませんが、塩分の摂りすぎは禁物です。
運動療法
運動することによって血流がよくなるとインスリンの効果が高まり、血糖値が下がります。運動によって筋肉量が増えることも、血糖値を下げる効果があります。ただし、どんな運動でも良いわけではなく、ウォーキングやジョギング、水泳などの「有酸素運動」が最適です。
薬物療法
糖尿病の薬は大きく分けて、飲み薬と注射薬があります。薬を投与することによって、血糖値を下げる働きであるインスリンの分泌を促進したり、糖の吸収を抑えたりする効果があります。
糖尿病の治療の基本は、上記の食事療法と運動療法です。そして、血糖値の状態やその人の体質などにあわせて薬物療法が行われます。
まとめ
立仕事や長時間での移動など、一時的に血流が悪くなって起こるむくみであればそれほど心配する必要はありませんが、頻繁に繰り返すむくみは病気のサインかもしれません。特に糖尿病が原因の場合、そのまま放置すると失明や足の切断などにつながりかねない深刻な合併症を引き起こす恐れがあります。
糖尿病を発症している場合、病院での治療と合わせて重要になるのが、自宅での血糖値コントロールです。食事療法や運動療法を続けるほか、糖尿病お助け隊では血糖値コントロールを強力にサポートする様々な商品も取り扱っています。
生活スタイルが多様化している中で、生活習慣が原因で発症する糖尿病の患者数は年々増加しています。自宅での対策もしっかりと行いながら、糖尿病予防・合併症予防に取り組みましょう。